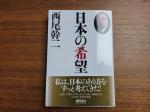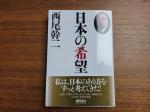
ゲストエッセイ(小山先生のブログより転載します)
小山常美 新しい歴史教科書をつくる会理事
西尾幹二『日本の希望』(徳間書店、2021年11月)を読んだ。誤読などもあるかもしれないが、印象に残ったこと、感じたことを記していきたい。
本書は、この30年間ほど、「日本」というものを思想的に、そして肉体的に背負って言論活動を行ってきた西尾幹二氏の、今という時点(あるいはここ20年間ほど)における言論をまとめた論集である。
欧米人が小泉首相の謝罪に点数を付けることへの不快感
「肉体的」という表現を使ったのは、例えば、2005年4月のバンドン会議で小泉首相が「侵略」と「植民地支配」を謝罪したときに欧米が日本を評価したこと、そのことに日本人が喜んだことに対して、西尾氏は単に精神ではなく、肉体からして不快になったのではないかと感じたからである。
氏は、《二つの世界大戦と日本の孤独》(『諸君!』2007年7月号/同年5月中旬執筆)という論文の「言葉による戦争が始まっている」という小見出し部分で次のように記している。
二〇〇五年四月バンドン会議で小泉前首相がわが国の「植民地支配」と「侵略」を例によって謝った。中国が折しも反日暴動に謝罪しない傲慢さで世界の非難を浴びていたさなかだったので、小泉演説は大人の印象を与え、政治的に点数を稼いだ。米紙ウォールストリート・ジャーナルは「今度は北京が謝罪する番」と書いた。欧米や国連の論調はたしかに日本に好意的だった。それだけにそのときだんだん私は腹が立ってきた。中国の強圧的無礼に屈した形になったことより、謝罪演説が欧米に評判がいいことの方が私にははるかに不快だった。
約九十カ国の代表が集っていたアジア・アフリカ会議の場である。そこで欧米人がアジア人である日本人に点数を付けている。しかもドイツと比較している。それを日本人が喜んでいるような構図自体が私には許しがたいことに思えた。アジアへの「植民地支配」と「侵略」をしたのはいったいどこの国だったというのであろう。……
アジア・アフリカへの「植民地支配」と「侵略」をそもそも日本の首相が謝るのはおかしいのではないか。しかもそれを欧米人に評価されて満足するような状況をつくる日本の政治家の歴史常識の欠如、自己主張の乏しさに、ただただ私は暗然たる思いがしたのだった。
323~324頁
全く正論である。本当におかしな構図である。植民地支配と侵略をさんざん行ってきた欧米人が日本人に点数を付けることなどできないはずである。だが、傲慢にもそういうことが行われたのである。その構図が、氏には「許しがたい」ことであった。
ブッシュ大統領が安倍首相の謝罪を受け入れるという構図への怒り
この文章につづけて、2007年に安倍首相が「慰安婦問題」についてブッシュ大統領に対して謝罪した件が取り上げられている。氏は次のように記している。
ひるがえって同じことは安倍首相の謝罪訪米にもいえる。慰安婦問題を謝るべきかどうかの前に、……首相が終始米国に向かって謝っていたことがいかに異様かということを言っておきたい。そしてブッシュ大統領が「首相の謝罪を受け入れる」と語ったことばも、いかに歴史常識から外れたばかばかしいポジションを米国がつねに日本に強要し、日本が唯々諾々とそれを受け入れているかを示すいい例証である。 324頁
安倍首相の謝罪の件は、さらにおかしな構図である。慰安婦問題で日本に何か落ち度があったと仮定したとしても、なぜ、アメリカ大統領がしゃしゃり出てくるのか。ブッシュに「首相の謝罪を受け入れる」資格などあり得ないではないか。この筋違いの構図、歴史常識から外れた構図に、西尾氏はあきれている。あるいは怒っている。
脱線するが、少し推測を働かせるならば、2005年から2007年にかけてアジアと日本との歴史認識の問題に米国がしゃしゃり出てきた動きは、恐らく、2006年の「つくる会」分裂ともつながっていたのであろうし、2015年の「安倍談話」や日韓合意にも一直線でつながっているのであろう。
話しを戻すと、こういうまっとうな感じ方をする人は、少なくともそのことをストレートに表現する人は、特に大物言論人の中では皆無のような気がするので、きわめて印象的であった。
以下、全体を構造的に紹介することはとてもできないが、特に印象に残ったこと、それと関連して感じたことを記していきたい。
まずは目次を掲げよう。( )の中は、参考のために私が記したものである。
Ⅰ
回転する独楽の動かぬ心棒に――今上天皇陛下に改元を機にご奏上申し上げたこと
(『正論』2019年6月号)
上皇陛下の平和主義に対し、沈黙する保守、取りすがるリベラル
(朝日新聞インタビュー、2017年12月14日)
講演筆録 歴史が痛い! (坦々塾、2017年10月1日)
宮内庁の無無為無策を憂う(『WILL』2021年9月号)
Ⅱ
言論界を動かす地下水脈を洗い出す――自由と民主主義とナショナリズムと
(『自ら歴史を貶める日本人』新装版まえがき、2021年9月)
そもそも「自由」を脅かすものは一体何か――日本学術会議問題の迷走
(産経新聞【正論】2020年11月19日)
私が高市早苗氏を支持する理由(産経新聞【正論】2021年9月17日)
Ⅲ
安倍晋三と国家の命運(『正論』2020年7月号)
「移民国家宣言」に呆然とする(産経新聞【正論】2018年12月13日)
日本国民は何かを深く諦めている(産経新聞【正論】2018年9月7日)
保守の立場から保守政権批判の声をあげよ(産経新聞【正論】2017年8月18日)
Ⅳ
二つの病理――韓国の「反日」と日本の「平和主義」
〔前編〕(『Hanada』2020年3月号)
〔後編〕(「問われているのは日本人の意志」『国家の行方』産経新聞出版、2020年2月刊、一部改変)
朝鮮は日本とはまったく異なる宗教社会である(『諸君!』2003年7月号)
Ⅴ
中国は二〇二〇年代に反転攻勢から鎖国に向かう(2020年4月5~11日執筆、『正論』2020年6月号)
日本とアメリカは現代中国に「アヘン戦争」を仕掛けている
――本来中国は鎖国文明である (『VOICE』2007年12月号)
歴史の古さからくる中国の優越には理由がない(産経新聞【正論】2011年1月12日)
中国に対する悠然たる優位が見えない日本人(『正論』2012年11月号)
「反日」は日本人の心の問題(『言志』14号、日本文化チャンネル桜、2013年10月)
Ⅵ
「なぜわれわれはアメリカと戦争をしたのか」ではなく、「なぜアメリカは日本と戦争をしたのか」と問うてこそ見えてくる歴史の真実(『正論』2011年12月号、改題)
今の日本は具体的にアメリカに何をどの程度依存しているか(産経新聞【正論】2016年6月10日)
ありがとうアメリカ、さようならアメリカ(『VOICE』2012年6月号)
Ⅶ
二つの世界大戦と日本の孤独(『諸君!』2007年7月号/同年5月中旬執筆)
Ⅷ
上皇陛下が天皇をご退位あそばされる頃合いに、
「陛下、あまねく国民に平安をお与えください」と私は申し上げました。
――あの戦争は何であったかを、私も陛下の同世代として生涯くりかえし問い続けてきたのです。(別冊正論33『靖国神社創立150年――英霊と天皇御神拝』2018年12月13日、産経新聞社)
あとがき
一 日本よ、生存本能を復活堅持せよ
トランプ大統領の日米安保不公平論に反応できぬ日本
体系的、構造的に論ずることはできないので、気になった順、印象に残った順に紹介していこう。最も印象的であり、最も私が大事だと思うのは、日本よ、生きる意志があるのか、生きる意志を復活させ堅持せよ、という西尾氏の声である。2011年以降、特に2016年以降、ほとんど月刊誌を読まなくなったから、西尾氏の文章を読むことはほぼなくなったが、昔から氏の文章を読んだとき、言葉に明確に表されていてもいなくてもいつも感じてきたのは、日本よ生存の意志を持て、という叫びだった。
この叫びが最も表されていると感じたのが、《二つの病理――韓国の「反日」と日本の「平和主義」〔後編〕》(「問われているのは日本人の意志」『国家の行方』産経新聞出版、2020年2月刊、一部改変)を読んだ時だった。
この論考は、トランプ大統領が唱えた日米安保不公平論の紹介から始まる。トランプ氏は、2019年6月28日~29日、G20大阪サミットの直前に、次のように不満を述べた。西尾氏の文章から引いておこう。
日本が攻撃を受けたらアメリカは参戦し、たとえ第三次世界大戦を引き起こすことになるとしても戦わなければならない。それに反し、アメリカが攻撃を受けた場合に日本は戦わなくてもよく、ソニーのテレビで戦争を眺めていればいいのだ、これは不公平だ、と彼らしい独特の言い回しで批判を述べた。率直かつストレートな表明で、語られた内容に疑問の余地はない。 144頁
ところが、トランプ大統領の問い掛けに、日本のマスコミでは誰も正直に反応しなかった。「日本の青年は安全地帯にいて、アメリカの青年は血を流して良い、という前提に立ついっさいの議論はもう通らない」(145頁)と日本側もわかっているにもかかわらずである。
反応しなかったのは、政界も同じである。「大統領は安倍晋三首相に再三再四にわたり、『安保不公平論』について語っていたと伝えられる」(同)。だが、日本の政治家は誰一人提起された問題を本気で取り上げなかった。安倍首相も同じだった。こんなチャンスはないのに、安倍首相はトランプの問題提起をふまえて9条改正論議をしようとはしなかった。9条②項を削除するか、解釈を変更して自衛戦力を肯定する方向に世論を持っていくチャンスだったのに、全くそのチャンスは生かされなかった。
自民党の右側に立つ政党を
なぜ、安倍首相は、このチャンスを生かせなかったのか。安倍氏自身の問題もあるが、諸外国の例を参考にすれば、自民党という名の「保守政党」の右側に立つ政党が存在しないことが一番の原因であろう。かつて、一時期、次世代の党という保守政党があったが、この政党が十分に根を下ろさないうちに潰したのが、安倍氏による2014年の解散総選挙であった。この選挙で次世代の党は事実上壊滅し、自民党という、実質的には半ば左翼リベラルの政党が一番右側に位置する体制が継続しているわけである。
話しが少しずれたが、西尾氏は、次のように自民党の右側に立つ政党の不在を嘆いている。
かくて私は、自由民主党の右側にかつての民社党のように筋の通った批判勢力が結集されなければこの国は救われないだろう、と臍を噬む思いで溜息を洩らしつつ事態の動きを深刻に見つづけているのである。 149頁
同じことは、《保守の立場から保守政権批判の声をあげよ》(産経新聞【正論】2017年8月18日)で、よりまとまった形で指摘されている。9条➂項加憲論というおかしな改正論が出てきたのも、結局は、かつての民社党のような自民党の右側に立つ政治勢力が存在しないからであるということが指摘されている。
生存の意志が見られない日本国家
話しを続けよう。上記引用のように、149頁で西尾氏は、安保不公平論に日本の政界が反応できないのは自民党の右側に立つ政治勢力がないからだと述べる。そして、上記引用に続けて次のように述べている。
たった一度の敗戦が戦争を知らない次の世代の生きんとする本能まで狂わせてしまった、というのが実態かもしれない。何としても生きなければならない、という自己保存の本能が消えてしまったとは思いたくないが、今日本はほとんど丸裸で、ミサイルを向けられると学校の子供たちが机の下に隠れるようにと防空訓練を発令する軍事的幼稚さ、非現実的内閣府通達が正気で出されたつい一年ほど前の出来事をうそ寒いことと痛感している。
先手を打つ敵基地攻撃以外に、ミサイルから身を守る方法はないのである。たった一度の敗戦で立ち竦んでしまうほど日本民族は生命力の希薄な国民だったのだろうか。 149~150頁
この文章に続けて、氏は、2003年8月26日産経新聞のコラム「正論」で記した文章を引用する。
「一つの有機体が衰微するときには、変化は内からも外からも忍び寄る。リンゴの芯も、腐る頃には、外皮もしなび、ひきつっている。国家も有機体である。内はシーンと静まり返って、死んだように動かない。そうなると、外から近づくものの気配にも気づかない。」 150頁
この文章は、私には印象的である。2003年時よりも「外から近づくものの気配に」気付く人は格段に増えている。だが、全体を俯瞰すると、日本という有機体は「リンゴの芯も、腐る頃には、外皮もしなび、ひきつっている」状態に見えるし、「内はシーンと静まり返って、死んだように動かない」。内部で動きはあるのだろうが、いかにも弱弱しいし、そもそも動き始めている人の数が少ない。私の印象だが、全体としては、何ら生存の意志を示せないまま、自滅に向っているように見える。
生存の意志、「何としても生き残ってやる」という想いは、日本の現状からは見えてこない。そもそも諸外国と異なり「核シェルターへの用意がほとんどなされていない」(156頁)し、防毒マスクや解毒剤が売られていない。私流に言えば、「日本国憲法」前文の思想のままに、諸外国に「日本人よ、お前たちは侵略と植民地支配に関する反省が足りないから、殺します」と言われれば、本当は殺されたくないのに何もできずに殺されてしまうような精神状態に、日本人は陥っているのではないかと思われるのである。
生きんとする意志を持とう
私流の言い方はともかく、生存の意志が見えてこない現状をふまえて、西尾氏は、この論考を「生きんとする意志」という小見出しの下、次のように締めている。
憲法第九条にこだわったたった一つの日本人の認識上の過ち、国際社会を感傷的に美化することを道徳の一種とみなした余りにも愚かで閉ざされた日本型平和主義の行き着くところは、生きんとする意志を捨てた単純な自殺行為にすぎなかったことをついに証拠立てている。 168頁
「たった一つ」という言い方には引っかかるが、言わんとすることは心から同感する。「国際社会を感傷的に美化することを道徳の一種とみなした余りにも愚かで閉ざされた日本型平和主義」を育ててきたのは、戦後日本の憲法学や国際法学、政治学でもあるが、それ以上に公民教育である。この日本型平和主義は、昭和20年代に強力に推し進められたのだが、平成に入って再び強くなり、とりわけ、グローバリズム万歳を強力に説く平成20年版学習指導要領が出て以降、ますます強くなっている。多少脱線して言えば、この延長上にヘイト法があり、昨年末の外国人に住民投票権を無条件に与えんとした武蔵野市住民投票条例問題があるのである。
ともかく、生きんとする意志自体を問題の俎上に上げ、日本よ、生きる意志をもてと言い続けている西尾氏の声を、日本人全体が受け止めるべきであろう。
二 日本は普通の戦争をしただけだ、自虐史観からの脱却を
なぜ、日本人は、生存の意志を示せないのか。それには、二つの理由がある。一つは、もちろん、東京裁判史観を学校教育やテレビ・新聞により、繰り返し注入されてきたからである。もう一つは、学者も含めて国民の多数が国家論を全く学んでこなかった結果、国家が国防という役割を持っていること、自衛権とはどういうものかということをきちんと理解していないことである。この二つの理由と相まって、「つくる会」は『新しい歴史教科書』と『新しい公民教科書』を出し続けている。『新しい歴史教科書』を通じて歴史教育を、『新しい公民教科書』を通じて公民教育を改善しようと試みているわけである。
韓国の反日の意味――繰り返し繰り返し日本人は韓国の言うことを聞け
西尾氏は、一つ目の理由に関連した言論を本書で展開している。その中で特に面白かったのは、韓国の反日思想、反日運動に関する見解である。それは、まず《二つの病理――韓国の「反日」と日本の「平和主義」〔前編〕》(『Hanada』2020年3月号)に見られる。
氏によれば、「文筆家の仲間を陰で批評するとき、『あの人は自分の背中が見えていない』という言い方をすることがよくある。文筆家同士でなくても、普通の社会人同士でも通用するものの言い方だ」(134頁)という。
「自分の背中が見えていない」人とはどういうものか。氏によれば、彼らは自分が評価されない理由をすべて自分の外に求め、評価する側が間違っていると考える。彼らは、自分の力不足が見えておらず、うまくいかない原因を他者に転嫁したがる。要するに、自分の周りの現実が見えていない人である。韓国人は、この「自分の背中が見えていない」人に当てはまるのではないかと氏は言う。
そして、西尾氏は、呉善花氏による韓国人分析を、次のように紹介し、賛意を表している。
「でたらめな基準で生きている日本人は、真の価値が理解できないからいつも頭を叩いておかないと何をするか分からない、と韓国人は考える。すぐ日本人は考えを変えてしまう。常にきちんと教え込んでおかないといけないのだ。韓国人の言うところの歴史認識とはこれであった。双方の国民がそれぞれ意見を主張しあって互いに歩み寄るというようなものでは決してないのである。日本人がやることは韓国が主張するものを受け取るだけ。反論や異論などとんでもない。繰り返し繰り返し韓国の言うことを日本人は心して聞けという、ということなんです」 138~139頁
傍線部にはびっくりした。韓国人の考え方がこういうものだとすると、黙って見送る以外に方法はない。お互いに主張し交渉し歩み寄るというスタイルはとりようがない。「日本人はすべてを承知したうえで、拒絶するものは拒絶する。そして付け加えて言うならば、許容と拒絶の境い目は相手が決めるのではなく、自分なりに予め決めておくべきなのだ」(141頁)ということになるのであろうか。
不幸せな史官という存在
次に《朝鮮は日本とはまったく異なる宗教社会である》(『諸君!』2003年7月号)という論文に見られる。この論文では、最初に、中国の史官のことが語られる。史官の仕事とは「事実を事実として枉げずに率直に記す。危険を冒してもそれをやる」(175頁)ことである。それゆえ、史官といえば、『春秋』をまとめた孔子も、『史記』を作った司馬遷も、『漢書』の班固も、皆、不遇のうちに死んだ。他の史書の書き手も、ほとんどが不幸な目に遭っている。
翻って、西尾氏は、『新しい歴史教科書』を作ったころから、この論文を記した2003年頃まで、「歴史教科書運動に携わる人はみな個人的に幸せにならなければいけない」(171頁)とよく言っていたという。
しかし、考えてみれば、「義務教育の歴史教科書は我が国では唯一の官許の『正史』」(同)である。ある意味、中学校歴史教科書の著者たちは史官である。中国の史官のように、『新しい歴史教科書』に携わる者、特に著者には幸せな生活は待っていないような感じがしないでもない。西尾氏自身、自分のことについて次のように記している。
私自身にしてからが、教科書運動に着手した頃から、私が属する学会の人間はひとり去りふたり去りして離れていった。いつの間にかNHKから声がかからなくなり、朝日毎日の文化蘭が原稿の注文をしてこなくなった。まさか古代中国のように誅殺されることはないだろうが、静かな老年の文章道にいそしむには、余りに烈しいテーマと課題に私はなお毎日取り巻かれている。 172頁
この史官の話や『新しい歴史教科書』関係の話をしたうえで、日本でベストセラーになった『親日派の弁明』の著者、金完燮氏が受けた苛烈な迫害について、7頁ほど割いて書かれている(172~175頁)。
韓国の反日思想の根拠――日本人は両班、中人、常民、賤民の下
金完燮氏に対する迫害を生み出すものは韓国の反日思想であるが、その思想について、元東京銀行ソウル支店長の湯澤甲雄氏から聞いた話が紹介されている。湯澤氏によれば、韓国の旧第一銀行で職員のストが始まったが、要求をすべて入れても加藤清正が云々と言い募っていて解決しない。
そこで調べてみると、彼らが気に入らなかったのは、能率本位で決められたオフィス内の座席配列であった。能率第一に考えて、すぐサービスのできる人をカウンター近くに、機器の近くには操作にたけた人を配置していたのだが、これが彼らには気が食わなかったのだ。それゆえ、古株は奥に、新米は外にというふうに変えたら、ストは止んだ。つまり、儒教的序列になおしたら解決したのである(180頁)。
この身分制的な意識こそが、反日思想の根拠となっている。本書によれば、朱子学を国教とした李朝以後の時代では、両班、中人、常民、賤民の四階級があるが、日本人は、この下の奴隷階級と位置づけられていた。
それゆえ、『明日への選択』2003年3月号所収の湯澤氏の論考によれば、韓国人は、日本人が過去に悪いことをしたから、反日意識を持つのではない。「絶対的に優越する韓国人が、絶対的に劣位の日本人に支配されたという現実が起きてしまい、自らを許しがたいと慙愧反省しつつ日本人はもっと許し難いというジレンマが反日となって噴出する」(182頁)のだという。要するに、韓国の反日思想とは、日本人差別思想からくものである。日本人が反省しても反省してもなくなるものではないのである。
では、なぜ、日本人は絶対的に劣位の存在として位置づけられてしまうのか。日本民族の主体は半島で生きられなくなった敗残の韓民族であるとする説が、韓国の歴史学者によって唱えられているという。とすれば、韓国人は日本人の先祖であるということになり、韓国人の儒教的考え方によれば、先祖である韓国人は子孫である日本人より優位の立場に立つ。しかも、半島での敗残者であるから、さらに日本人は劣位に位置づけられて当然だということになる。両班、中人、常民、賤民の四階級の下に位置づけられて当然だ、絶対的に劣位の存在だ、という理屈になるわけである(184~185頁)。
国家の格を守るために尖閣は守らなければならない
目次に記したⅣの部分が対韓国をテーマにしたものだとするならば、Ⅴの部分は対中国をテーマにしたものである。そのうち、《中国に対する悠然たる優位が見えない日本人》(『正論』2012年11月号)で記された次の言葉が印象的であった。
戦後の日本は経済力が国家の格を支えてきたが、逆にいえば、国家の格が経済力を支えてきたともいえるのである。尖閣はだからこそ、経済のためにも死に物ぐるいで守らなければならないのだ。 237頁
国家の格が経済力を支えてきたという捉え方は、言われてみれば、なるほどと思わされた。第二次大戦で手ひどい目に遭った日本とドイツが、戦後世界において経済大国となったのは、やはり、その歴史に基づくものであろう。共に軍事強国であり政治大国であった日独は、そのことを一つの遺産として国家の格を守り、経済大国になったと考えられよう。だが、尖閣という小さな領土さえも簡単に奪われてしまうようであれば、国家の格は一挙に下落し、経済も更に地盤沈下していくことになろう。
アメリカの虎の威を借る中韓
次に、Ⅴの部分で印象的だったのは、《「反日」は日本人の心の問題》(『言志』14号、日本文化チャンネル桜、2013年10月)の中の一節である。この2013年の論文は、「アメリカの虎の威を借る中韓」という小見出しの下、次のように記している。
今の日本人にとって「反日」外国人の代表は韓国人と中国人であろう。けれども彼らはそもそも戦後の最初から親日的ではなく、その点でずっと変わらなかった。とりたてて敵意を込めた「反日」が彼らにおいて最近激化しだしたのは、アメリカの出方と関係がある。旧戦勝国アメリカがあらためてわが国に敗戦の事実を再認識させ、再占領政策を強いていると日本人が感じ始めた情勢の変化に関係がある。そして中国が同じ旧戦勝国の名でこれに同調し、韓国が戦勝国でもないのに、これに悪乗りしている状況の不当さにも関係がある。 244頁
保守言論界では、世界的な反日言動の中心には中国がいるという議論が盛んだったが、西尾氏は、いや、むしろ米国が中心であり、中韓はアメリカの虎の威を借りているのだと言うのである。つまり、歴史戦の主敵は、対中韓、特に対韓問題を利用したアメリカ(正確にはアメリカ民主党)ということになる。だが、日本の保守政治家と言われる人たちのほとんどは、「アメリカ占領軍の歴史観をそのまま鵜呑みにしている観があり、再三失望した」(246頁)と西尾氏は言う。氏によれば、防衛問題に見識があるとみられる石破茂氏や前原誠司氏も、小泉進次郎氏や小泉純一郎氏も、弁舌力と気迫で抜群の橋下徹氏も、全員が「反日」の徒である(同)。
中韓との問題から逃避してはいけない
このように述べたうえで、西尾氏はさらに、最近は、中韓以外のアジアの国々の親日ぶりを報告する論文や書物が目立つが、これはあまり良いことではないという。日本はいいこともやっていた、を主張したがるのは、悪いことをやっていたことを前提として認めているのである。つまり中韓の側が悪いこととして定めている内容を承認した結果なのである」(247~248頁)。
それゆえ、日本は、対中韓の問題から逃げてはいけない。「中韓の側が悪いこととして定めている内容を承認」してはいけないのである。
「なぜアメリカは日本と戦争をしたのか」という問い
こうして、対韓国、対中国の問題は、対アメリカの問題に行きつく。Ⅵ、Ⅶ、Ⅷでは、対アメリカ問題が論じられていく。Ⅵの初っ端の論文は、「なぜわれわれはアメリカと戦争をしたのか」ではなく、「なぜアメリカは日本と戦争をしたのか」と問うてこそ見えてくる歴史の真実(『正論』2011年12月号、改題)である。
戦後の日本人は、「なぜわれわれはアメリカと戦争をしたのか」という問題設定ばかりしてきた。その結果、「あの戦争を日本の犯罪という人はさすがに少なくなった」(250頁)が、ほとんどの人が日本の失敗だと考えてきた。
だが、本当にそうか。「日本の失敗ではなくて、アメリカの失敗ではないか」。「アメリカの歴史に過失があり、歪みがあり、それが原因で日本はとんでもない迷惑、大被害を蒙った」のではないか。「アメリカが自分の都合で太平洋に進出し、日本との戦争を組み立て、日本を襲撃したと考える見方があってよいのではなかろうか」(同)。
このように問題設定したうえで、西尾氏は、アメリカ史と世界史の流れを追いかけ、次のような結論、というよりも仮結論に至っている。
私は先にアメリカは膨張国家だと書いた。しかしその膨張の仕方はロシアともイギリスとも中国とも異なる。アメリカは本当は膨張する必要がないのに、建国の理念、宗教的に自らを「正義」の民とするイデオロギーのために膨張せざるを得なくなっているのではないかとの疑念に襲われることがある。もちろんそこにもうひとつ資本の論理が重なってくる。 263頁
「疑念」という書き方であるから、この2011年の論文では仮結論に過ぎないであろうが、これより後の論考を読むと、本当は膨張する必要がないのに膨張したという捉え方は、西尾氏の中で強固に存在するように思えた。
結論か仮結論かはともかくとして、「なぜアメリカは日本と戦争をしたのか」という問いかけをして物事を見ていくと、アメリカの不正義、アメリカの出鱈目さがよく見えてくることになる。この見方をすることによって、西尾氏は、アメリカの押し付けてくる東京裁判史観から脱却し、日本は普通の自衛戦争を戦っただけだ、ナチス・ドイツのような「人道の罪」は全く犯していないと自信を持って主張することができるわけである。
アメリカと三年半も戦争できたことは成功だった
そして、「あとがき」では、膨張する必要がないのに膨張してきたアメリカと戦ったことを明確に、前向きに肯定している。氏は、次のように日米戦争について記している。
日本の船出は成功でした。第一、アメリカと三年半も戦争ができた。しかも襲い掛かってきた苦難を敗北主義ではなく、敢然と受けて立ち排除しようとして敗れたのであり、これには悔いはないのです。ほかに手段もなかったのです。戦争を引き受けないでいたら、戦後のみじめさは倍加して何もしなかった国家に襲いかかってきたでしょう。戦ったゆえに尊敬もされ、決して屈辱と敗北主義の濡れ衣だけで日本が沈んでしまったわけではない。その日本再興の目は、アメリカが力を衰弱させている今、そして中国が目茶苦茶な国であることがわかった今、日本の戦争も再評価される時期を迎えつつあるのではないだろうか。 361頁
このように氏は、最初の傍線部にあるように、敗戦も含めて日米戦争の遂行を前向きに捉える。そして、二番目の傍線部にあるように、日本の今後に希望を見いだしている。本書のタイトルも「日本の希望」と付けている。
三、家族、民族、国民国家、ナショナリズムの優位性
家族、民族、国民国家、ナショナリズムこそが自由と民主主義を守る
では、なぜ、西尾氏は、希望を見いだしているのであろうか。歴史認識が変化していき、日本の戦争が再評価されるだろうという予測も一つの理由だろうが、もう一つ、より重要な理由は、国民国家やナショナリズムの方が世界連邦やグローバリズムよりも自由や民主主義を守り育てるものである、という考え方を氏がとっていることであろう。この点については、Ⅱの《言論界を動かす地下水脈を洗い出す――自由と民主主義とナショナリズムと(『自ら歴史を貶める日本人』新装版まえがき、2021年9月)で記されている。
自由と民主主義は大切である――そこまでは大方の人の意見が一致する共通ラインかもしれない。しかし、そこから先が問題なのだ。家族、民族、国民国家、ナショナリズム―――これらが自由民主主義の敵ではなく、むしろ自由と民主主義の側にあり、各国の歴史をみても自由と民主主義を守り育ててきた母胎であると今私が言い切れば、まだ百の反論が出て来そうな雲行きであるかもしれない。けれども逆に、移民の自由、国連中心主義、世界連邦、グローバリズム―――これらこそが自由と民主主義の味方であり、民族のエゴイズムを克服して、人類が格差をなくし、永遠の世界平和を実現する高い理想の目標価値そのものにほかならない、と言い切れば、これまた首を傾げる人が限りなく現れるであろう。単に理想が高いからではなく、民族のエゴイズムを否定するそのことが人間の本性に反し、もしこれを無視して強引に人類共生の理として通そうとすれば、美しいワンワールドの名においてどこかの一民族が史上例のない新しい「帝国主義」を実現することに手を貸す以外のいかなる結果をも将来しないであろう、と想定されるからである。 58~59頁
このように氏は、家族、民族、国民国家、ナショナリズムと移民の自由、国連中心主義、世界連邦、グローバリズムとを対比させているが、明らかに氏の立場は前者の側を支持するものである。
グローバリズムは自由と民主主義の敵対者である
しかも、世界の動きを見ると、国民国家やナショナリズムの方がグローバリズムよりも自由と民主主義を守るものだとする見方が広がっていっていると氏は捉える。次のように述べている。
おそらく十~十五年ほど前まで、あるいは人によっては最近まで、家族、民族、国民国家、ナショナリズムと並べ立てられたら、否定的概念の連鎖として次に起こるのは独裁主義、全体主義、ファシズム、帝国主義、そして戦争の誘発というふうに相次いでネガティブな言葉が口を継いで出てきたのであろう。そういう鸚鵡返しの思考訓練が学校教育と新聞テレビ等のメディアによって国家内部においてほとんど無意識の自動運動として行われてきたからである。しかし、世界の動きを冷静に見ている者の目に、全体主義や帝国主義を引き起こす主体はナショナリズムではなく、むしろ国境の壁を低くする運動に端を発したグローバリズムの方だと考えられるようになってきている。 64~65頁
グローバリズムは、家族、民族、国民国家を解体しようとしているし、当然、特に欧米や日本のナショナリズムも否定する。そして、この論文で氏も述べているように、グローバリズムの担い手である国際金融資本も中国共産党も「選挙の洗礼を受けずに人民や国民を支配している」(66頁)し、国際金融資本が支持する米国のバイデン政権は、自由と民主主義の原則を無視して大規模な不正選挙によって、その権力を手にした。明らかに、グローバリズムは自由と民主主義の敵対者になっているのである。
以上、本書を、生存本能、自虐史観からの脱却、家族、民族、国民国家、という三つの問題に焦点を当てて紹介するとともに、特に印象に残ったこと、思ったことなどを記してきた。誤読などあれば、御寛恕をお願いしたい。
転載自由