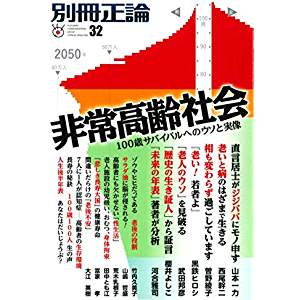
「最近の一連の仕事をまとめて」の(D)別冊正論が発売されています。
私も今早速読んでいます。
誰でも年は取ります。今高齢の人ばかりでなく、
もうすぐ高齢になる人、
また高齢になる近親者がいる人にも、
是非読んで欲しい内容ばかりです。西尾論文は
「老いと病のはざまで―自らの目的に向かい淡々と生きる」です。日録管理人長谷川
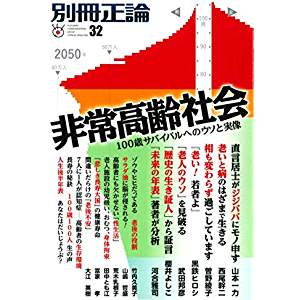
「最近の一連の仕事をまとめて」の(D)別冊正論が発売されています。
私も今早速読んでいます。
誰でも年は取ります。今高齢の人ばかりでなく、
もうすぐ高齢になる人、
また高齢になる近親者がいる人にも、
是非読んで欲しい内容ばかりです。西尾論文は
「老いと病のはざまで―自らの目的に向かい淡々と生きる」です。日録管理人長谷川
『正論』11月号に「安倍総理へ、『戦後75年談話』を要望します」という論文を出しています。談話のやり直しを求める内容で、私の歴史観を語っています。ご参考にして下さい。
渡辺 望氏自身による紹介文
次に『未完の大東亜戦争』の紹介を記したいと思います。この本のテーマをアスペクト出版の編集者の貝瀬裕一さんから提示されたとき、とても嬉しい気持ちでした。なぜかというと、ずっと以前から私が書いてみたいテーマだったからです。「本土決戦とは何か」ということは、高校生くらいのときからずっと考えていたことでした。
今年は集団安保法制云々のことがあっから余計そうだったのでしょうけど、8月15日周辺になると、憲法学者や近代史学者を中心に平和主義の合唱がメディアでおこなわれることにうんざりという方は勿論少なくないでしょうけど、うんざりするだけでなくて、どうしてこういう面々がこの国に多いかということを考えなくてはいけないと思います。よく、日本は有史以来、たいへん恵まれた存在で、きわめて早い段階から統一国家、国民国家を形成することができ、そして他国から蹂躙されたことのない幸せがあったということを聞きますが、まさにその「幸せ」が、平和主義のぬるま湯風呂をつくってしまったのではないだろうか、と私は毎年、8月になると思うのですよ。
もし、8月15日以降も戦争が継続したらどうなっただろうか。これは間違いなく、たいへんな不幸が日本に訪れたと思います。核兵器の大量使用、米ソによる日本の分断、皇室の存続の危機、そして言うまでもなく気の遠くなるような戦死者。昭和天皇が聖断の御前会議で言われたように、この世界から日本がなくなってしまうかもしれないほどの悲劇がこの国土を蹂躙したかもしれません。しかしそのような悲劇がもしあれば、今の体たらくな日本の左派、平和主義者などがいなことも事実ではないか。そのすさまじい日本本土決戦の仮想上の悲劇は、果たして日本人にとって「不幸」なことなのだろうか。私自身は、8月15日の終戦をもっとも妥当とする「穏健論」にういつまでも依拠しています。しかし依拠しつつも、この現在の日本の精神的不幸の根源を模索するために、「終戦が早すぎた」=日本本土決戦という思考実験の必要を感じるのです。
以上の視点から、いろんな角度から日本本土決戦を検討してみたのですが、たとえば「本土決戦」というと何か日本人にとってとてつもなく恐ろしい存在に思えますが、世界の国民国家間の戦争はほとんどが「本土決戦」だという事実がありますね。また昭和20年当時、内地にいたいろんな日本人知識人の手記に描かれている「本土決戦」=竹槍での戦い、のイメージは、実は8月6日の原爆投下以前の地上戦のものでしかない。「核兵器が使われる日本本土決戦」の想像というのをおこなう前に戦争が終わってしまったともいえます。それから大本営の一部には、1944年に日本本土に連合軍が侵攻してくると考えた面々もいました。もしそんなことがおきたら、大東亜戦争の終結と日本本土決戦は別個の問題になりますね。そんなふうに、「日本本土決戦」の想像というのも、実は単一ではないんですね。
また、アメリカにとっても日本本土決戦はたいへんな歴史的苦境でした。日本本土決戦がおこなわれて、日本軍と国土義勇隊が沖縄戦・硫黄島戦並みの抵抗をすれば50万人の死傷者(ベトナム戦争でのアメリカの死傷者は39万人)が予想されたからです。この数字に怯えて、マンハッタン計画に異常な熱意を傾けたのがトルーマンであり、また陸軍長官スティムソンらは日本への降伏条件を緩和すべきという立場を展開しはじめたりもする。ところがマッカーサーは、日本本土決戦を自分の軍人人生のフィナーレとするヒロイズムにこだわり、総計で140万人の地上軍、42隻の正規空母と24隻の戦艦を投入する地上最大の作戦=日本本土決戦に執拗にこだわり、トルーマンと対立します。この対立、そして「日本本土決戦のやり残し感」が、その後の朝鮮戦争などに重大な影響をもたらすことになります。
一方、スターリンはすべての秘密情報を把握しつつ、ソ連にとっての最大限の利益を日本列島の地図を前にして毎日考えている。またイギリスはイギリスで、日本本土決戦により大東亜戦争が長期化すれば、南方に取り残された300万の日本兵が植民地独立勢力と結託して反英ゲリラになることを恐れ、日本への降伏条件をなるべく緩和するべしとの立場を主張します。要するに、1945年夏の世界情勢は、日本本土決戦を中心に動いていたということができるでしょう。日本人はとかく、日本人の視点からしか日本本土決戦のことを考えたがらないですが、こうした世界情勢の中での日本本土決戦への思考ということは、たいへん大事なことだと思います。
けれどこうした客観的視点をおおいに投じても、最後は当時の日本人の精神がどうだったかということを問題にしないといけなくなります。核戦争にせよ、地上戦にせよ、対米ソ両面戦争にせよ、日本人が本土決戦に挑むには「滅亡」を覚悟しなければならないのは厳然たる事実でした。このような「滅亡」の覚悟を、日本人は有史以来経験したことがなかったのです。しかし、この「滅亡」を全肯定し、「日本本土決戦をなすべきであった」という危険なロジックに足を踏み入れ、そしてついにそれを完成させてしまったのが三島由紀夫でした。この紹介文では省きますが、本書ではところどころに、三島由紀夫のこの本土決戦論のかかわりについて触れ、考察を展開しています。三島のあの自死でさえ、本土決戦論と重大な関係があると思います。ある意味で本書は裏道からの三島由紀夫論といえるかもしれません。
また後半部分では、純軍事的側面から、日本本土決戦のシミュレーションの章も設けました。8月15日以降も戦争が続いた場合、「鈴木貫太郎内閣で戦争が継続するのかそれともそれ以外の内閣で戦争が継続するのか?」、「アメリカは原子爆弾を日本本土決戦にどれほど生産投入することが可能だったか?」「ソ連軍の南下のスピードはどれくらいか?」「天皇の聖断とアメリカの対日降伏条件融和派が一致を見せることはありえたのか?」「本土決戦がおこなわれた場合の特攻作戦の戦果は?」などの諸要素について考察しています。これらの思考実験を通じて、「思想としての日本本土決戦」とうべき史学の分野の生成に資することができればと思い、終戦の季節に刊行完成いたしましたのが本書でございます。
林 千勝さんご自身による紹介文
自著に寄せて
『日米開戦 陸軍の勝算―「秋丸機関」の最終報告書』(祥伝社新書)
林 千勝
「敵を知り、己を知れば百戦殆(あやう)からず」(孫子)
私もそう考えます。
こういう考えの私が、七十年前のあの戦争の「開戦」の決断に関する真実を追求してきました。その結果、驚くべき真実に出会ったのです。
決断は、人間の精神活動の中で、あるいは組織行為の中で、最も高次のものです。ましてや、七十年前のあの戦争の「開戦」の決断です。言うまでもなく、あの戦争は「総力戦」です。「総力戦」とは、すべての国力を挙げて、より本質的に言えば、国民経済を挙げて戦う戦争のことです。決断には、すべての国民の生命と生活がかかっていました。本書では、「総力戦」の経済的側面を重視しなければならないとの観点から、戦争戦略の策定における客観的な数字データを読者の皆様にそのままお見せします。供するものは一次資料です。この一次資料には、当時、陸軍省内で実際に行われました戦争シミュレーションが含まれます。「開戦」の決断を後押しした戦争戦略の策定プロセスにおいて、枢要な位置を占めていたイギリス、アメリカの立場での経済的な側面を重視した戦争シミュレーションです。本書では、このシミュレーションを当時と同じ形で体験していただきます。このことにより、本書において、対米英戦開戦という空前の意思決定を行った東條首相や杉山参謀総長と、そこに至るまでの思考過程を共有することになります。同じ目線を持っていただきます。要するに、「開戦」の決断過程の追体験です。 ―― まえがきより抜粋
わずか70年前の歴史の真実、強く志向された「生」、主体的な「行動」、そして研ぎ澄まされた高い「認識力」。―― 戦前日本(昭和)では、政府や軍当局も、言論界も、すべてを認識していた。政治・経済・軍事を地球規模で俯瞰し、敵を知り己を知っていた。70年前の戦争の開戦の決断は、完全経済封鎖により追い込まれに追い込まれた末のもの。対米屈従の道を選ばなかったこの決断は、国が、民族が、家族が生き残るためであり、それゆえ、極めて合理的な判断の下に行われた。そうでなければ、国民は納得せず、国家は運営できず、陛下もご裁可なさらなかった。実際、「持久戦に成算無きものに対し戦争を始めるのは如何か」が昭和16年当時の陛下のお考えであられた。そして、この判断の主役は陸軍であった。
陸軍は「生きるか死ぬか」のぎりぎりの決断を下すために、敵と己の経済抗戦力の測定とそれに基づく戦略の策定に知見を最大限に発揮した。同時に、ドイツの苦戦も視野に入っていた。そして、科学的な研究に基づく合理的な“西進”主体の戦争戦略「対米英蘭蒋戦争終末促進に関する腹案」を、昭和16年11月15日大本営政府連絡会議にて決定し、続いて果敢に行動したのであった。―― 結局、日本は一部海軍勢力の作為によりこの戦争戦略から逸脱し敗北したが・・・・。戦後これまで、この戦争戦略の存在が歴史の中に埋もれていた。況や、この戦争戦略がどんなプロセスと裏付けをもって作成されたかは完全に歴史から消されていた。
70年前の戦争で植民地を次々と解放した日本の戦いぶりを見て、世界の支配者たる白人たちはその底力を恐れた。だからアメリカは、日本占領とともに戦争の真実、日本の「生」と「行動」と「認識力」の軌跡を消した。日本人の魂を圧殺し、歴史をつくり変えた。邪魔な書物を没収し、言論を統制し、ラジオ、新聞、映画そして教科書などで日本人を洗脳した。邪魔な当局文書もほぼすべて没収した。更に、アメリカ監修で二次資料をつくり浸透を図った。戦後あてがわれた日本の歴史、特に戦争をめぐる歴史は、大事な部分がフィクションだ。歴史の闇は深い。われわれは、アメリカとGHQによって消された記録と記憶のすべてを「発掘」しなければならない。知性の責務だ。「発掘」される“昭和のダイナミズム”は、現在の日本人に対して求心力を及ぼす。日本人の「本源性」を呼び覚ます。これは、日本人の精神の軸に関わる問題であり、思想戦上の展開でもある。われわれには思想戦上の反転攻勢が必要だ。―― だから、私も本書でささやかな一石を投じたい。
注:8月12日のプライムニュースの動画を完全版にしました。
管理人
鈴木敏明さんご自身による紹介文
「大東亜戦争は、アメリカが悪い」の英文版「The USA is responsible for the Pacific War」が一昨年8月に300部出版した。日本滞在の外国の大使館、領事館合わせて185ヶ国に贈呈した。著者の私としては、外国の図書館や外国のメディヤにも贈りたい。印刷会社に1万部と10万部の印刷料聞くと、およそ3百76万円、と3千100万円になると言う。これでは資金的に手も足も出ない。ベストセラーの小説でも書いて印税かせがなきゃとても無理。とても無理でも兎に角書いてみようと思ったのだ。私が若い頃、「野望に燃える男」というアメリカ映画があった。当時のイケメン俳優、トニーカーティスが、映画では普段さえないホテルのウェイターだが隆とした背広を着こみ青年実業家を装い大富豪に接近し、大富豪の子供の姉妹に近づき、彼女たちをたらしこみ、大富豪を乗っ取ろうとする映画です。今でも「野望に燃える男」という題名を覚えているので、いつ頃の映画だったか調べてみた。ウイキペディアでトニーカーティスと「野望に燃える男」を一緒にして検索してみるとくわしい説明書きが出てくるのにはびっくりした。この映画1957年の制作です。私はその時19歳。横浜の三流ホテルでボーイをしていた頃だ。小さなホテルだからボーイの他にもウェイター、ベッドメイキング、バーテンダーの手伝い、バーの掃除などいろいろやらされた。バーの掃除の時は、いつもレコードをかけながら、とくに好きだった「カナディアンサンセット」は何回もかけながら掃除をしていた。そんな頃私はこの映画を見たのだ。私はこれまでほとんど公言してこなかったが、私の人生は波乱万丈、仕事も波瀾万丈なら異性も波瀾万丈なのだ。若い頃社会的底辺の仕事をしていたが、少しも暗い影はなかった。私は若い頃はイケメンでものすごく女性に持てたからだ。「野望に燃える男」の映画を見て思わず「俺もいざとなったらこの手が使えるな」と考えたものだ。そのため「野望に燃える男」というタイトルが私の心から消えることもなくいまになっても覚えているのだ。そんなことで苦労話や興味のある体験談なら事欠きません。面白い小説を書いてやろうと書き出していた。しかし、あまりにも面白くしてやろうとそればかりを意識しすぎたせいか、書き終わってみるとあまりにも長すぎて焦点のぼけた小説なってしまった。今度は余計なものはけずりにけずってやっと仕上げた。しかし書き込むのはいいが、けずるという作業はむずかしいものだ。何かとてもいい話をけずるような気がしてならなかった。それでもけずったお蔭でまともな原稿が、ことしの前半にできあがった。360頁ほどの小説です。
本来ならここで私は数々の出版社まわりをし、出版のお願いをして原稿を置いてくるのでしょうが、知名度なにもなしの私が初めて書いた小説です。その上今月喜寿を迎える77歳の老人、私の人生の賞味期限もおよそあと10年、出版社まわりをしていつ出版してくれるかを待つ悠長な時間はない。私は自費出版を決断した。自費出版では、ベストセラーがさらに生まれにくくなることは確かです。私が「大東亜戦争は、アメリカが悪い」を自費出版した時は、今から11年前、その時とは自費出版業界は、様変わりに変わっています。今ではどこの出版社でも自費出版しているのだ。そのため数はあまり多くないが自費出版でもベストセラーが出ているのです。私はこれまでに宝くじなど買ったことはありません。今度はベストセラーという一等賞を取るために自費出版という宝くじを買ったのです。宝くじの一等賞をとるのは非常にむずかしい。しかしベステセラーという一等賞がとれなくても、それなりに売れなければ、私の筆力不足、能力不足としてあきらめることにした。
まず四社、中央公論社、新潮社、幻冬舎、文芸社から合い見積もりをとった。私の原稿に対四社の書評は、良かった、しかしけなしたら出版社も商売にならないから、その分書評も割り引いて考えねばならないでしょう。一般的に自費出版の場合は、初版千部での見積りになります。初版千部の見積りの他に重要な物が四つあります。
1.初版千部は、いつまで売ってくれるのか?出版期間はいつまでか?
大東亜戦争は、アメリカが悪い」の場合は、一年の出版期間だった。一年で千部以上売れなければ、それで出版契約は、終わり。ところが一年で三千部も出版したのだ。出版社は、こんな本売れないだろうと予測し、本の大きさ、厚さを考えると1500円では安すぎるのに定価にしてしまったのだ。売れても損をすることないが、儲けがほとんどないことになる。倒産したから良かったが、倒産してなければあわてて定価を変えねばならなかっただろう。2.印税の詳細、初版も二版もそれ以降も同じか、自費出版初めての人、私のように何回か出版の経験もあり、ブログを長期間書いている人、当然印税に違いが出る。
3.チラシ広告、100部、500部など出版費用に含まれているかどうか?売るためにはチラシ広告は、絶対に必要ですし、またどういうチラシにするか著者の意見も必要です。
自費出版でチラシなどいらないということは、自分で売り込みはしないということです。自分の書いた本を自分で売り込まなければ、誰が売り込んでくれますか。4.支払条件
小さな自費出版社なら、分割払いを進めます。倒産の場合の被害を少なくするためです。これらの四つの出版社の見積りの総合評価の結果、私は文芸社と自費出版契約を結んだ。今から11年前私が初めて自費出版した時、文芸社も自費出版社として存在していた。以来自費出版社として成長し、今では自費出版社だけの出版社としては最大で、草思社(出版社)を100パーセント子会社化しています。自費出版だけで食べているだけに、他の三社、中央公論社、新潮社、幻冬舎よりも自費出版には、一日の長があることがわかった。文芸社は、今二つのベストセラーを抱えています。
1.「それからの三国志」
サラリーマンが定年後に自費出版をした歴史小説です。現在20万部売れているそうです。
2.「本能寺の変、431年目の真実」
明智光秀の子孫が、このかたサラリーマンであったかどうか知りませんが、自費出版した。歴史事件の捜査ドキュメントです。これも今30万部売れているそうです。この本の二つのタイトルを見ると、ベストセラーになる小説は、本のタイトルからしてベストセラーになる雰囲気があるような気がします。それに引きかえ私の本のタイトルではベストセラーになる雰囲気はないし、タイトルを今更変えることもできないし、変えるにしてもアイデアは浮かばないし、このままのタイトルでベストセラーになる夢を見ることにしよう。本が売れれば「大東亜戦争は、アメリカが悪い」の英文版は海外にも行き、日本語版の再出版も可能になるのだ。本は8月末に本屋から売り出されます。皆さん、ぜひ買って読んでみてください。本のタイトルは、「えんだんじ、戦後昭和の一匹狼」、定価は1600円プラス税です。
渡辺望さんご自身による紹介文
この『大東亜戦争を敗戦に導いた七人』と『未完の大東亜戦争』の二冊の本の依頼をいただいたアスペクト出版さんは、パソコン関係で有名なアスキー傘下の総 合出版社ですが、最近は歴史・政治関係の書籍に進出していて、特に佐藤健志さん、倉山満さん、古谷通衡さんといった若手の保守系評論家の本を次々に出して います。「今までとは違う保守系の本」をつくっていきたい、ということです。私への依頼もこの流れの中でのことでした。
まず一冊目の『大東亜戦争を敗戦に導いた七人』ですが、大東亜戦争の戦後七十年、何を考えなくてはいけないかという問題意識から書いています。戦後「七十 年」の前は六十年、五十年が論壇や政界で大きく問題になったし、そして「七十年」の後は百年、百五十年ということが待ち受けているでしょう。私などからするとこのような果てしない時間的儀式の繰り返しは、はっきりいって徒労感をおぼえる。たとえば「戦後」ということなら、日露戦争にも戦後ということはあるけれども、日露戦争の「戦後」は少しも問題にならない。日露戦争の終戦戦勝記念日である9月5日を記憶している日本人がどれほどいるでしょうか。
「敗戦」ということがこの大東亜戦争の戦後の果てしない時間的儀式と関係があるのでしょう。国際法規が戦争状態を規定し、また大東亜戦争の戦勝国がその前後でさんざんに戦争を引き起こしている現実からして、「開戦」ということ自体には歴史的に何の犯罪性も問題性もないことは、多くの日本人はわかっているはずです。また戦争法規違反という中韓を中心とした日本への戦争責任追及にしても、彼らが証拠をでっちあげていることが多々あり、こうした「犯罪を偽造する犯罪」は、刑事法規の世界では虚偽告訴・誣告の罪といって、たいへん重要な罪なんです。つまり中韓などの国は「戦争犯罪を虚偽した戦争犯罪」法廷をつくらなければならないようなことをしているわけです。要するに、平和主義勢力
や中韓国家の言うレベルでの戦争責任は逆立ちしても成り立つわけがない。成立するとしたら、それを受け入れている日本の現実が逆立ちしているのです。
結局、「敗戦」ということについて、日本国民自身がそれを導いた日本人を歴史法廷に訴える、ということのみが「戦争責任」だということになるわけです。このことが明確化されないまま、いや明確化されないからこそ、「戦後~年」の儀式は延々と続いてしまうことになっていると思います。同じ「敗戦」でも、たとえば七世紀の白村江の戦いでの大敗では、開戦を主張した斉明天皇や中大兄皇子らの「開戦責任」は少しも問題にならず、敗戦責任を日本の統治機構のシステムの不備にあるとして、律令制度の確立と整備をおこないました。以降、律令制度は形骸化の時期を含めて約1200年の長きに渡り日本を拘束しますが、やはり白村江の「敗戦」、敗戦責任の記憶の拠り所がそこにあって、律令制度を見る度に敗戦を克服できたから、という視点も可能だと思います。いずれにしても七世紀の日本人の方が、二十世紀・二十一世紀の日本人に比べて、遥かに明晰に「敗戦」と「戦争責任」に向かいあうということができていたのではないでしょうか。
ただし、七世紀の日本人は、「誰それに敗戦責任がある」というような歴史法廷の場まで持つことはありませんでした。その時代の日本は大人すぎたといえるかもしれません。その感情の蟠りのようなものが、その後しばらく、壬申の乱その他の陰惨な政治劇を生み出した面があると思います。七世紀の白村江の戦いと二十・二十一世紀の大東亜戦争の二つの敗戦の両方に欠けていた「歴史法廷」の場を大東亜戦争に関してつくり、「戦争責任=敗戦責任」の所在とそれを有する歴史的人物を明示することを本書の課題とした積りです。山本五十六、米内光政、瀬島龍三、辻政信、重光葵、近衛文麿、井上成美を「敗戦責任者」とした人物選択と敗戦責任の内容については、この紹介文では省かせていただきたく思い
ます。
 |
「正義」の嘘 戦後日本の真実はなぜ歪められたか (産経セレクト) (2015/03/18) 櫻井よしこ、花田紀凱 他 |
◎目次
はじめに 何が戦後日本を一国平和主義に閉じ込めてきたか 櫻井よしこ
第1章 慰安婦問題だけではないメディアの病 櫻井よしこ×花田紀凱
第2章 イデオロギーのためには弱者を食い物にする 櫻井よしこ×花田紀凱
第3章 「けちな正義」の暴走 西尾幹二×花田紀凱
「朝日」は世界中の戦時売春を告発するがよい!/朝日の「ドイツを見習え、個人補償」論/ドイツが個人補償をする理由/そして「慰安婦問題」だけが残った/朝日の「けちな正義」/ドイツの凄まじい管理売春/「強制連行」したドイツ軍/戦争がある限りなくならない問題/相手の「罪悪」を思いださせる反論
第4章 世論はこうしてつくられる 潮匡人×花田紀凱
第5章 軍事はイメージとイデオロギーで語られる 古谷経衡×花田紀凱
第6章 勘違い「リベラル」と反日 門田隆将×櫻井よしこ
第7章 朝日新聞が歪めた事実と歴史 櫻井よしこ×西岡力×阿比留瑠比×花田紀凱
あとがき 花田紀凱
昨年は当ブログにおける私の文章の更新は少なく、このことに関する限り不本意でした。お詫び申し上げます。
病気したわけでも海外旅行をしたわけでもなく、全集の刊行が難しい局面を迎え、編集校正に追われ、しかも昨年内刊行予定の第10巻が遅延して1月刊となる不始末でした。間もなく刊行されます。
第10巻は『ヨーロッパとの対決』と題し、世界に中心軸は存在しないこと、西欧は閉鎖文明であること、西欧の地方性、周辺性、非普遍性を、ドイツやパリで言って歩いた記述を元に展開しています。
たまたま『GHQ焚書図書開封』⑩は『地球侵略の主役イギリス』という題で年末に刊行されました。西欧の先端を走ったイギリスの閉ざされた闇を問いました。
ただこの本はそれだけでなく、第1章「明治以来の欧米観を考え直す」に注目していたゞきたいのです。近年ウォラスティーンなどに依存し、再び西洋中心史観に溺れかかっている現代日本の歴史の学問、人文社会科学系の学問一般に疑問を突きつけています。
もうひとつ『正論』連載の「戦争史観の転換」も第11回を迎え、スペインからイギリスに移動したヨーロッパのパワーが中世以来のカトリック政治体制の闇を背後に秘めてアジアに向かってくることを論じ始めています。
以上三つの仕事がどれも手を抜けず、息もつけない有様で、昨年はあっという間に一年が過ぎました。三つの仕事が期せずしてバラバラでなく、一つの結論に向かって同一方向を目指していたことに自らやっと気がつき、計画外のことでしたので、吃驚しております。
以上三つの歴史像が今私の中でひとつになって熱っぽく回転しています。今年もその駒を回しつづけることになるでしょう。
皆さまのご健勝を祈ります。
(追記)『GHQ焚書図書開封』は①~⑤の徳間文庫化が始まりました。
 |
GHQ焚書図書開封1: 米占領軍に消された戦前の日本 (徳間文庫カレッジ に 1-1) (2014/10/03) 西尾幹二 |
 |
GHQ焚書図書開封〈2〉バターン、蘭印・仏印、米本土空襲計画 (徳間文庫カレッジ) (2014/11/07) 西尾 幹二 |
 |
GHQ焚書図書開封〈3〉戦場の生死と「銃後」の心 (徳間文庫カレッジ) (2014/12/05) 西尾 幹二 |
 |
GHQ焚書図書開封10: 地球侵略の主役イギリス (2014/12/16) 西尾 幹二 |
 |
見て・感じて・考へる (2014/10/20) 池田 俊二 |
添え書きの口上 西尾幹二
私はいつもの悪い癖で、ぎりぎりまで本書の草稿の拝読を怠っていて、著者から再校ゲラも出たのであと一週間しか待てないと言われて慌てて拝読に手を着けた。私の横着がいけないのだが、ちょうど急ぐ仕事が幾つも重なっていて、時期も悪かった。
途中まで読んではたと困った。私が何か添え書きするのはまずいなとさえ思った。私らしき人物が登場し、その主張的立場を語っているからである。著者が私を尊敬しているというスタイルになっているだけに、私が私をプロパガンダすることになり兼ねない個所が生じている。本書の刊行を祝って口添えするのは恥しいだけでなく、厚かましくもある。しかも私の主張的立場は必ずしも正確には伝えられていない。これも当惑している点である。
よほど添え書きをお断わりしようかと思ったが、今となっては時すでに遅く、出版に差し障りが生じるかもしれない。というより、右の問題点以外には私が発言しない理由は何もなく、本書の内容そのものは私にとって魅力的であり、ページをめくるごとに共感同感の連続である。そこで、読者はどうかご了解いただきたいのだが、私らしき人物に関する部分はなかったことにして――再校も出ている段階でそこを全部削ってくれといまさら言うのは無茶なので――そういう前提で以下をお読みいただきたい。
著者の池田俊二氏は私の『人生の深淵について』の生みの親で、私がものを書く仕事のスタートラインに立ったときの目撃証人のような方だった。私の全集14巻『人生論集』の後記でこのいきさつを詳しく語っている。氏を「刎頸の友」とそこで呼んでいる。
本書は一人の老人が死ぬ前にどうしても言っておきたい世の中への怒りの証言のようなものともいえるが、それは同世代の私が共有しているものでもある。文鳥はだしに使われているだけで、あらずもがなであり、文学効果をあげているとも思えない。ただ、これがないと著者は多分書きにくかったのだろう。自己韜晦の仮面に使っているのである。それほどにも怒りは深く、強く、内攻的でもあるからである。気の合う友人や元同僚、同じ思想を持ち合う二人の娘婿に囲まれている終(つい)の栖という舞台設定も、同じような仮面、表現をしやすくするための著者の工夫でもあるが、似たような生活場面が著者の日々の暮しの中にあるのではないかと推定される。そうした知的環境の中に生きている老後の「主人公」は幸わせでもある。しかし噴き出す思いは烈しく、正直で、生々しくて、ストレートである。若いときから押し殺してきた感情、官庁勤務で表現を阻まれていた思想、しかしどう考えても世の中一般の観念やメディアの通念が間違っていたことは、次第に歴然としてきている昨今の情勢である。それを考えると、何であんな分り切ったばからしさが社会を圧倒していたのか、不思議に思える。著者は若いときから完全に軽蔑しきっていた人や思想がある。しかし世の中がかつてそれらを正道のごとく担ぎ回っていた歴史がある。思えばその歴史において著者は孤独だった。その孤独感を偲べばこそ今の怒りは鮮烈である。
その意味で本書の中で私がいちばんリアリティを感じたのは最後のエピソードである。同窓会で亡くなった二名の友への追悼演説が回想されている。早稲田のロシア文学科に行った友人が共産主義の夢から目覚めたのは新聞社のモスクワ支局長になってソ連を実地体験してからであった。「現場を見てからでなくてはほんたうのことが分らないやうでどうするか。我々は文字を持つてゐる。ものを見ずとも、文字、書物により真実を知ることはいくらでも出来る。」と著者は叫んだ。もう一人の物故者には東大の全学連闘士であった。「何が日本にとつてのプラスなのか、人類にとつてのプラスなのかを考へないのか。時の風潮といふやうなものを情状として私は認めない。」
これでは追悼演説ではなくて弾劾演説ではないか、と本文中に対話者の相手に言われてしまうが、このエピソードはひょっとして実話ではなかろうか。同窓会でこれに似た立居振舞があったのではないか。真相はもちろん知る由もないが、この場面の扱いだけが身内や親友を相手にした室内の気安い対話ではないのである。第三者に向けた公開の口上なのである。
そのことが何を意味するかを考えた。孤独がここだけ破裂している。
考えてみれば私のような評論家は社会的にこの「破裂」を繰り返して来ている。第三者に向けたこの手の「公開の口上」を課題とし、職業化している。それだけに同窓会のような場面では決して口を開かない。無駄口を噤んで穏和しくしている。怒りや軽蔑感を気取られぬようにしている。本書の著者にしても平生は多分そうだろう。永年の官庁勤務の社会生活では自己を隠蔽しつづけて来たであろう。
本書ではその孤独感がいかに重かったかをいかんなく示す。同じ苦渋を内心に深く抱えて生きている人は少なくなく、否、最近は言葉を求めてあがき出している人々がメディアの空文化の度合いに比例して増えつづけていると私は観察している。本書はそういう人々の喝を癒やすカタルシスの書でもある。しかし、ただ単にそういうことに心理的に役立つ一書であるのではなく、戦後の日本の病理学的な「心の闇」がいまだに克服しがたく、ここを超えなければ今後の日本に未来はないことへの倫理的な処方箋を、思いがけぬ裏側の戸口を開いて見せてくれた一書であるといえるだろう。
尚、文中に出てくる鴎外、漱石、荷風の文学、あるいは乃木大将をめぐる文学談義の質の高さは、本書が高度な趣味をもつ文人気質の知識人の筆になることをも証してくれている。著者が旧仮名論者であり、福田恆存の心酔者でもあることをお伝えしておく。
平成26年9月23日