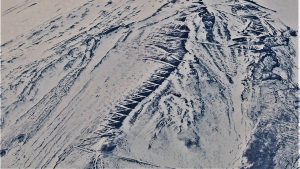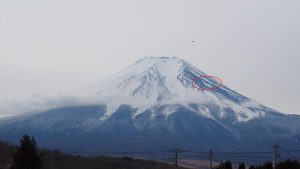ゲストエッセイ 坦々塾会員松山久幸
昨秋、久し振りで会った大学同期の水上氏が、「もう支那では現金が使えないよ。一般のクレジットカードですらダメで、それを使えるのは精々ホテルのフロントくらいかな。上海では乞食だって現金は受け取らない。」と語っていたのがずっと気に掛かっていた。
大日本帝国陸軍下士官で若い頃は関東軍兵士としてソ満国境近くで任務についていた今は亡き父が、生前ときどき話していた満洲の奥地に少しでも近づきたいと思い3年ほど前に訪ねたみた。大連からJRパクリの新幹線に乗り遼寧省の瀋陽(奉天)、長春(新京)、哈爾濱(ハルピン)の三省都を巡った。その時には現金とクレジットカードだけで充分に用が足りた。そんなこともあり、水上氏の話していたことは本当かいなとの思いで再び大連を行ってみたのである。
思えば食品関係の仕事で20年ほど前に大連に出張した頃は、日本の面影を宿す家屋が所々に点在しとても懐かしく感じたものである。しかし今はその古い建物は殆ど取り壊され、開発に次ぐ開発で高層ビルが林立し様相は激変した。
大連市の総人口は約600万人で都市部は200万人だという。そのうち日本企業関係者は19万人にものぼり、10人に1人は何らかの形で日本企業と関係している。因みに日本の企業は1550社が大連に進出していて、これは上海、バンコクに次ぐ規模なのだそうだ。街のあちこちで日本語の看板も目にする。
街を歩けば直ぐ気づくことだが、昔は通行人の信号無視は当たり前で走る車を縫って通る人を良く見かけた。今はルールを守る人が多くなって来ているようだ。
今回は2路線ある地下鉄にも乗ってみた。社内アナウンスは北京語と英語。そして駅名のおよそ半分くらいはその後に日本語と韓国語のアナウンスが続く。韓国人も相当入り込んでいる証拠だろう。確かにカラオケの機器・ソフトは殆ど韓国製。だからテロップの日本語歌詞はときどき変なのがあったりする。
街を歩く若い夫婦連れにも注目してみた。滞在3日間で2人の子供を連れた若夫婦にはたった2組しかお目に掛かれなかった。残りはみな1人っ子。その1人っ子が祖父母4人から溺愛されるものだから甘ったれて育つのは当然のこと。慌てた政府が軌道修正したものの、歪な人口構成が将来的に必ず現出する運命にある。
小生至って昔気質で女性の喫煙を端なく思っている。煙草を吸う女性を見るとどうしても夜の街角に立つ女を連想して仕舞うのだ。ましてや人前で化粧する女なぞは論外中の論外。電車の中などで斯様な女性を見掛けると、「お嬢さん!ここは化粧する所ではありませんよ。」と必ず窘めることにしているが、大連は日本よりもっと酷かった。ただし注意するのは控えた。ここは外国であるしどんな仕返しが待っているか分からいからだ。日本でも1度
「痴漢!」と車内で大きな声で喚かれたこともある。
訪れる度に発展が著しい大連だが、東港という地に何とイタリアのヴェニスを模した街が突如出現したのには驚いて仕舞った。運河もありゴンドラも揺ら揺ら。ディズニーランドの様な娯楽施設でもなく街として作られていて、ここまでやるかといった感じ。大連駅近くにロシア人街が残されているが、いま何でイタリアのヴェニスなのかよく分からない。そう言えば「一帯一路」にイタリアが参加するそうで、そのことも関連しているのかも知れない。その周辺には真四角の細長い高層ビルも数棟建っているが、人の気配はせず、もしかしてあの「鬼城」かなとも思ったりした。ここは市の中心部からはかなり離れた所にある。
歩き疲れて入ったマクドナルドでコーヒーを飲みながら客を見ていて気が付いたことがある。何人かの人は店に入っては来るが、何も注文せず空いている席に座りスマホを暫く弄ったりしてそのまま黙って出て行く。まあ日本でもやろうと思えば出来ないことはないが…。
昔に比べて大部きれいになったタクシー(全てフォルクスワーゲン車)にも乗ってみた。殆どのバス停や街角の至る所に監視カメラが設置されているのが見える。犯罪捜査には威力を発揮するであろうが、彼の国の主目的はそれではなかろう。
勝利広場に近い市場には様々の果物が所狭しと並べて売られている。イチゴとサクランボがおいしそうで毛沢東の肖像が入った人民元札でどちらも買い求めた。値段は日本の半値くらい。現金は全く問題なく流通していた。各店にはQRコードが貼り付けてあり、それに自分のスマホを翳し決済している客をたまには見掛けるものの、ここ大連では未だ現金が主流のようである。ホテルに帰って部屋で賞味したが、イチゴはなかなか美味かった。もしかして日本のイチゴの種で作られているのかも知れない。
2日目の午後、労働公園からそう遠くないところにある松山寺を訪ねてみた。唐代の玄宗皇帝の頃に創建された歴史あるお寺で、よくぞこの共産党政権下で存立出来ているなとの思いである。さほど広いとは言えない境内には堂々とした五重塔も聳え、地元の人と思われる2~3人の参拝客が長い線香を手に熱心に拝んでいたのが印象的ではあった。正月には大連に住む日本人の多くが初詣に訪れるという。このお寺は松山家の菩提寺という訳ではないが名称に親しみを覚え、大連に来た時には必ず参拝することにしている。
この度の3日間の旅でまず感じたことは、行く度毎に雑然とした街が段々と整備されて来ていることだ。ドヤ街的な所はあっという間に取り壊されて大きなビルが建っていたりする。街を歩く人々の服装も日本とさほど変わらない、彼らの心の中まで覗くことは出来ないが、共産党独裁国家で政治的自由は許されずとも、それに反発しなければ、物資は市場に溢れていて国民は日々暮らして行けるのだ。今回は乞食もたった1人だけ見掛けたくらいである。
それに引き換え我が国は、政治的に自由であると言っても独立国として必須の国軍もなく、国の安全保障はアメリカに依存していて本当の意味での独立国家であるかは疑わしい。経済的に如何に豊かではあってもそれは砂上の楼閣に過ぎないだろう。
益々豊かになったが政治的自由を持たない大連の人々を見て、独立心を失って久しい我が国の人々とが二重写しに見えて仕方がなかった。(令和元年6月記)