カテゴリー: 未分類
12月7日プライムニュース
阿由葉秀峰が選んだ西尾幹二のアフォリズム「四十回」
西尾幹二先生のアフォリズム 第6巻 坦々塾会員 阿由葉 秀峰
(6-1)過去の思想はすでに歴史に固定され、動かないものとしてわれわれの前にあるのではない。今なお新しく評価され、批判され、われわれの内部に運動を引き起こす流動体として存在しているのである。いな過去の思想はそのものとして存在しているのではけっしてない。われわれがそれによって体験をかち得たその結果として、はじめて過去の思想は存在するにいたる。
(6-2)宗教に対するある理解の仕方が正解であったか、誤解であったかは合理的に決められることではない。誤解によっても人は信仰を得ることができるし、認識を拡大することができる。そしてそれが結果として正解に触れ、それを包みこんで増殖していくことがありうる。
(6-3)人は「正解」を知っただけではなんにもならない。それは単なる知識である。知識で人は生きることはできない。「客観的な事実」とは近代人のもっとも陥りやすい錯覚の一種である。
(6-4)誰でも他人の不幸を見て心愉しむところがあるが、それはまだ悪人とはいえない。他人の不幸によって自分が安堵するというなにほどかの利益があるからである。しかし本来の悪人は、自分にはなんの利益もないのに、他人の不幸や苦悩を見て限りない愉悦を覚える存在であるとされる。この種の悪人にとっては他人の不幸や苦悩をみることそれ自体が目的になる。
(6-5)近世哲学が確立されて、人は石が下方に向かうという本質をもつものであるとは考えず、石がいかなる条件のもとにいかなる仕方で下方に向かうかだけを研究するようになった。つまり自然現象の根底にある不変の本質を求めるのではなく、自然現象の法則を求めることに、自らの探究の範囲を限定したのである。これによって自然科学は確立した。と同時に近世の哲学は、それ以降自然科学のこの確実性と矛盾しない道を歩まざるを得なくなった。
(6-6)すべてを説明し、なにも選択しないのは、現代知識人のもっとも好むところであろう。
(6-7)近代の批判的精神は、瞞されまいとする意識を人に与え、人はそのこと自体に結果として瞞されている。「正解」とはそうであって欲しいという学者の単なる願望にすぎないのではあるまいか。
(6-8)中国で爛熟してから日本に渡来した大乗仏教を基に、千数百年信仰を支えてきた自分自身の生活経験を度外視して、近代の仏教学が成り立つということは、なんとしても私の常識には反するのである。ヨーロッパの学者が指し示した阿含経典と、日本に渡来した密教化した大乗経典の間には千年くらいの落差があるはずであり、自分自身のこの重い経験をあっさり抹殺するに足るほど「原点」という二文字への恐怖心が強かったのだろうか。
(6-9)何千何万という経典をことごとく仏説とする東洋人の不合理は、キリストの直接の言葉を唯一の規範(カノン)にする彼らにとっては納得出来ないことであったに違いない。しかしそれはあくまで彼らのお家の事情である。少し冷静になってみれば、西洋人が小乗仏典を根本経典と定めたのは、宗教の合理化と無神論の進行した十九世紀西欧の精神状況となんらかの形で関係があったくらいのことは、考えることが出来たはずであろう。
(6-10)つまり仏教とはいかなる規定をも拒む、外延の広い概念で、それゆえに数万の経典はすべて仏身と言い得て懐疑の生じなかった所以でもある。
にも拘わらずこれに接した西洋人は、つねに規範(カノン)を大切にし、一定の視点からしかものを見ようとはしない。
(6-11)キリスト教の根柢にユダヤ教があり、ユダヤ教がより根源的であるからといって、べつだん西欧カトリックの正統派の信仰はそのこと自体で揺らぐようなことはない。ヴェーダやウパニシャッドと、中国渡来の大乗仏教に培われた日本人の信仰との間にも、当然、この関係が成り立ってしかるべき筈なのである。
(6-12)近代意識の先駆とみられる江戸時代の富永仲基は、『出定後語』においてなるほど西欧人より百年も早く聖典を歴史の産物とし、小乗経典に着目し、近代の実証研究の成果に匹敵する見解を述べてはいるが、しかしまた同時に、彼は実証の不可能ということ、最古の仏説を文献から抽出することは不可能であり、無意味であることにも気がついていたのである。仲基は「(シャカの直説に近いものを見出しうる)其の小乗の諸経でさへ、多くは後人の手に成りて真説は甚だまれなるべし」と述べ、認識の限界への強い知的懐疑を表明している。これをみると、批判の進んだ現代の仏教学者より、江戸時代の人間の方がいかに思索の力が勁かったかが分るだろう。
(6-13)正解とは何か。それは一片の知識にすぎないのではないか。(中略)信仰を失ったことの最もあからさまなしるしとして、文献学を信仰している、という以上のことではあり得まい。
(6-14)過去がたとえ誤解であり、擬似であったにいせよ、われわれは自分の過去を払い捨ててしまうことは出来ない。しかし過去を大切にする姿勢までが、少しでも古い根源に遡及したいとする知的欲念となって、近代の原理に支配され勝ちであることをわれわれは忘れないでおきたい。過去を愛することと、過去を通じて自分を主張することとは、元来、別個のことである。
(6-15)歴史を相対化するということは、一種の破壊行動であるけれども、さりとていったん認識が開かれれば、破壊を避けることはできないという矛盾がある。それは当然のことであり、すべての学問が背負う宿命でもあります。
(6-16)私は概して社会に変化を望まない。なにかが良くなるように期待する前に、これ以上悪くならないようにと祈るだけである。
それは私が理想を信じないからでは決してない。社会のなかで実現が期待できる程度の理想を、ことごとく軽蔑してやまないからにほかならない。
私はなにかが可能だと語る人にたいして、これまでつねに、はたしてほんとうに可能だろうかという疑問だけを突きつけてきた。私には現実の堅い壁が気になる。なぜ人は壁の一部を少しでも改修することから仕事を始めようとしないのだろう。なぜ壁をいっぺんに取り毀し、自分は壁の向こう側に立っているという見取図で物事を語り始めるのであろう。そういう人々の理想は、私には少しも理想には見えない。それは空想にすぎない。
(6-17)未来は必ずこうなる、だからわれわれはこうすべきだという類のあらゆる確言、あらゆる断定を語る者は、私の目にはすべてアジテータに見える。
(6-18)人間も生物である以上、未知の事柄にたいしては、たとえ望ましいと思う事柄にでも、慎重に、おずおずと手探りしながら向かって行くしか生き方を知らないものなのだ。真の理想家は現実の堅牢さ、リアリティの不動の重さを知っている。現実を良くするように期待する前に、これ以上悪くならないようにと祈願する、(中略)
真の理想家は現実の改善改良など頭から軽蔑しているからである。そんなことよりも自分の内心の理想がはるかに巨大だからである。また、そのような理想家でなければ、現実はほんとうには見えてこないのではないだろうか。
(6-19)ひとつひとつの具体的事例でエゴイズム、すなわち人間の愚劣で惨めな側面がわれわれの制度や社会の仕組みの基本を決めているのであって、そのような最低基準に理想を求めるべきではなく、愚劣な現実にはあくまで現実の道を行かしめよ、現実を変えることが理想だと思って安心するほどに小さな理想家であってはいけないということが、肚の底から分かっているひとはむしろ少ないといえるだろう。もしそうでなかったら、現実を少しばかし小手先で変えることを理想だと思って、理想と名づくものがたいがい安っぽい社会的解決をめざして、〝戦争のない世界〟であるとか、〝差別のない社会〟であるとかいった名称で飾られることはないだろう。
(6-20) 社会だの制度だの、それに関わる人間の心などに徒らに理想を求めるのではなく、ショーペンハウアーがいうように、どうせ人間の社会的心性に改善の余地はないものと大悟徹底して、環境を良くしようと考えるよりも、悪くしないようにだけ気を付けよう、と覚悟のほどを固めておけば、われわれはお互いによほど住みよい環境を作ることができるのではないかと思うのである。
ところが、世の中にはこれが分かっていない人が、とりわけ知識階級に跡を絶たず、おかげで世間をよほど住みづらくしている。
(6-21)われわれがショーペンハウアーのように人間に期待せず、人間を虚栄と利己心に満ちた愚かで哀れな存在として正視し、その限界点ですべての問題を眺めているなら、どこかの外国に理想をすぐ求めたり、その空想的な基準で日本人を責めたりはしないであろう。また、美化された理想を日本社会に押しつけた場合に、ばかばかしい混乱と無意味な葛藤が生じるだけだという、起こり得ることのいっさいの想像図を、リアルに思い描くこともできるであろう。
(6-22)現代の知識人はあまりに理想が小さすぎる。それゆえ現実を冷たく突き離して見ることができないだけでなく、そもそも現実そのものが見えない。
(6-23)現代の知性は不合理なるものをすでに信じていないというが、だからといって真の合理性を具えているとは、必ずしもいい難いのである。
(6-24)もし、歴史学者が個人的色彩を消すのに成功したならば、それによってより高い客観性が獲得されるということはけっして起こらないだろう。逆にあらゆる歴史的判断の基準を失い、とめどない相対性の泥沼の中に落ち込むだけであろう。例えば私は私の個人的な感覚、思考、判断力、さらには発想の癖というものまで排除してしまえば、私は私を理解できないばかりでなく、他人を理解することもできなくなるはずである。なぜなら他人は私を通じてしか理解し得ないものだからである。豊かな芸術的経験と感受力とをもたない者はいかなる芸術史をも記述できない。たとえ「私」を消し去ることが意図であったとする客観的な歴史記述がある成果を収め得たとしても、成果のうちには意図からはみ出たものが生きているはずである。
(6-25)歴史はわれわれがどんな風に未来を生きようとしているかという問題によって限定されてはじめてわれわれの前に現われるものであろう。その意味で、歴史はけっして過去からくるものではなく、未来からくるものである。ヨーロッパの歴史意識が、「終末」へ向かうキリスト教的な時間の観念と不可分であるといわれるのも、「終末」がはじめてわれわれの存在に意味と統一とを与えてくれるからであり、そのような目標というものをそなえている未来への緊張を欠いてしまっては、そもそも歴史意識は成り立たぬからであろう。人間が過去を決定するのは、人間が未来に決定されているからである。
(6-26)人間がみずからの主(あるじ)たるためには、人間の上に主たる存在を設定しなければならない―これは人間性の本質にかかわるパラドックスであろう。みずからがみずからをよく統御しうるためには、人はすすんで被統御者の位置につかなければならないのだ。個人は全体の中で自己の位置を知り、部分としての自己の限界内に徹することで、はじめて個人としての自覚を得る。だが、この現代において、人為的・人造的な全体者以外に、いかなる主が可能であろうか。が、考えてみれば、このように近代人が全体者を見失ったのは、近代人みずからが全体者たろうとしたからではなかったのか。部分としての人間がひとりひとり世界の主人公であることを主張しはじめたためなのだ。
(6-27)近代人は、人間の上にいかなる主をも認めようとはしなくなった。この人間への信頼、過信こそ、歴史主義の基礎でもあろう。
(6-28)過去は現代のわれわれとはかかわりなしに、客観的に動かず実在していると考えるのは、もちろん迷妄である。歴史は自然とは異なって、客観的な実在ではなく、歴史という言葉に支えられた世界であろう。だから過去の認識はわれわれの現在の立場に制約されている。現在に生きるわれわれの未来へ向う意識とも切り離せない。そこに、過去に対するわれわれの対処の仕方の困難がある。
(6-29)過去とのつながりを切られたときに、人間は歴史的基盤を失う。そういうとき、人間は単なる現在のうちに立ちつくし、未来への方途をも見失う。
出典 全集第六巻
ショーペンハウアーとドイツ思想 より
「Ⅰ ショーペンハウアーの思想と人間像」より
(6- 1)(26頁下段から27頁上段「ショーペンハウアーの虚像をめぐって」)
(6- 2)(70頁上段「西欧におけるインド把握の原型」)
(6- 3)(70頁上段から下段「西欧におけるインド把握の原型」)
(6- 4)(74頁下段「西欧におけるインド把握の原型」)
(6- 5)(99頁「神秘主義に憧れた非神秘家」)
(6- 6)(101頁「神秘主義に憧れた非神秘家」)
「Ⅱ ショーペンハウアーの諸相」より
(6- 7)(121頁「インド像の衝突」)
(6- 8)(123頁下段「インド像の衝突」)
(6- 9)(124頁上段「インド像の衝突」)
(6-10)(125頁上段から下段「インド像の衝突」)
(6-11)(129頁下段「インド像の衝突」)
(6-12)(136頁上段「インド像の衝突」)
(6-13)(136頁下段「インド像の衝突」)
(6-14)(137頁上段「インド像の衝突」)
(6-15)(150頁下段「富永仲基の仏典批判とショーペンハウアー」)
(6-16)(152頁下段から153頁上段「侮蔑者の智恵」)
(6-17)(154頁上段「侮蔑者の智恵」)
(6-18)(155頁上段「侮蔑者の智恵」)
(6-19)(160頁下段から161頁上段「侮蔑者の智恵」)
(6-20)(161頁上段「侮蔑者の智恵」)
(6-21)(163頁下段「侮蔑者の智恵」)
(6-22)(163頁下段から164頁上段「侮蔑者の智恵」)
(6-23)(164頁上段「侮蔑者の智恵」)
「Ⅲ 歴史と永遠」より
(6-24)(188頁下段から189頁上段「ヨーロッパにおける歴史主義と反歴史主義」)
(6-25)(195頁上段から下段「ヨーロッパにおける歴史主義と反歴史主義」)
(6-26)(202頁上段から下段「ヨーロッパにおける歴史主義と反歴史主義」)
(6-27)(202頁下段「ヨーロッパにおける歴史主義と反歴史主義」)
(6-28)(207頁下段「カール・レーヴィット『ブルクハルト―歴史の中に立つ人間』」)
(6-29)(210頁下段「カール・レーヴィット『ブルクハルト―歴史の中に立つ人間』」)
激動する世界、私たちは?
チャンネル桜「秋の特別対談」より
九月「保守の真贋」の出版(二)
あとがき
私は、自分は保守主義者であると言ったこともなければ、保守派の一人であると名乗ったこともありません。保守という概念は私のなかで漠然としていて、自分の問題として理論武装したことがありません。ただ今回は少し違います。表題と副題に示したとおり、「保守」を積極的に使用しました。われながら大胆であるとびっくりしています。
日本の今の政治に対し物申す抗議の思いにおいて、本書は切なるものがあり、私の見解や主張を誰にでも分かるように効果的に打ち出すうえで、「保守」は便利な記号でした。
ある人、ある人々が賢者であることを自己宣伝している場合に、賢者であることはいかに困難で希有な例外であるかを示しさえすれば、彼らが愚者であることを論証しなくても、賢者でないことは自ずと明らかになるでしょう。ある人、ある人々が勇者であることを売り物にしている場合には、真の勇気とは何であるかを説明しないでも、彼らのたった一つの臆病の事実を指摘することに成功しさえすれば、勇気を誇示した彼らの物語は、総崩れしてしまうでしょう。
同様に今の日本で「保守」の名の上に胡座をかいている自由民主党とその指導者たち──たいがいは二世三世議員で、努力しないで栄冠をかち得ているリーダーたち──は、本物の保守の正しい条件を示されれば、いかに「保守」の名に値しない人々であるかを思い知らされるでしょう。そして、リベラル左派となんら変わりのない言動の事実を一つでも指摘することができれば、保守政治家をめぐるすべての名誉ある物語は崩壊し、雲散霧消してしまうでしょう。
「保守」は元来、人気のない、嫌われ言葉でした。「保守停滞」「保守頑迷」「保守反動」……等々の使われ方が示すように、良いイメージは少なく、政党名に用いられることは日本では不可能でした(本書・の二、参照)。私が大切にしているのは保守的な生き方であって、政党政治上の保守ではありません(本書・の一、参照)。ところがどういうわけか近頃、人気のないこの悪者イメージに少し変化が生じてきたのです。
理由は分かりません。「保守的」であることを若者が好むようになってきました。この付け焼き刃的な、風向きしだいでどうにでも変わる、あまり根のないムード的な保守感情は、なにごとであれ事を荒立てることを好まない今の日本社会の体質とも合致していて、「保守」は安全で穏健なイメージをかち得ていて、プラスの価値づけがなされているのです。安倍晋三氏を「右翼」呼ばわりしながらも最大多数で公認している日本社会の空気の流れは、この中途半端さにぼんやり漂うように生きることを好む今日の日本人の生ぬるい性向をこのうえなく象徴しています。学校名にも商品名にも使いたがらない「保守」という字句、選挙用ポスターにも用いたくない「保守」というネガティブな概念がやっと日の目を浴び、恰好のいい風格ある言葉として浮かび上がってきているのが昨今です。そして安倍氏が退陣しても、自民党はなおしばらく日本社会の保守体制(エスタブリッシュメント)として君臨し続けるでしょう。
しかし、われわれはいつまでそれを許していてよいのでしょうか。この政党と政治家たちは日本と日本国民の首をゆるやかに絞め続け、やがては窒息死に向かわせてしまうのではないでしょうか。本当の「保守」とは、こんなものであってよいわけがありません。本書・の一の後半において、真の保守の五つの表徴を掲げておきました。これに引き比べ安倍政権のやってきたこと、あるいは何もしなかったことは徹底的に批判されるべきです。
彼らよりさらに保守的な、安倍氏の及びもつかない思想が日本にはあります。日本民族の存続が問われる思想の要点が今述べた五つの表徴ですが、日本のマスメディアがこれを逃げ、「極右」とか「ポピュリズム」とか一括して乱暴に葬り去るのを安倍氏と自民党はうまく利用していて、自分たちを最右翼の安全な現実主義者であるかのように演出しています。保守言論知識人も自民党の応援団の域を出ないので、同じ間違いを犯しています。 極東の空と海が一触即発の危機に迫られている現下において、国民の不安と恐怖をよそに、自民党の内部と周辺に、民族の生存を懸けた真実の発語はなく、シーンと静まりかえっています。岸田文雄氏も麻生太郎氏も小泉進次郎氏も石破茂氏も、もはや期待できません(彼らはすでにお蔵入りです)。自民党の奥の方から首相の寝首を掻く兵(つわもの)はなぜ出てこないのでしょうか。
安倍晋三氏は、アメリカから「修正主義者」と呼ばれました。国内では「右翼」呼ばわりされています。じつはこれは「贋の保守」だということなのですが、そのことが「真の保守」の登場を阻んでいるのです。真の賢者や真の勇者にあらざる者に「贋の賢者」や「臆病者」のカードがきわめて有効であるように、安倍晋三氏と停滞する自民党にカードを突きつける場合に、「保守」はこのうえなく便利な符丁です。
本書『保守の真贋』は、「真の保守」の存在する可能性を示し、党内党外を問わず、政治の流動化を止めている局面の淀みを打開するよう訴えているのです。
自民党の現状よりもずっとましな保守グループがなぜ出てこないのでしょうか。「日本ファーストの会」という名の団体が出てきたようですが、民進党の落ちこぼれ組と手を組もうとしているところを見ると、とうてい本物の「保守」の任に耐えられるものではなさそうです。
今までの「保守」が「保守」を邪魔しているのです。選挙のたびに自民党に入れたくない浮動票が「受け皿」を探している時代です。本書を読めば、「真の保守」の何たるかが分かるでしょう。正々堂々と今までの自民党を保守の立場から批判する個性、ないし団体の登場が今ほど待たれているときはありません。外圧であれ、小内乱であれ、今までの贋の秩序を根底から組み替える力がどこからか働かないかぎり、わが国の未来は救われないでしょう。
私自身は保守といい、革新といい、いかなる政治概念(イデオロギー)も信じていません。何度も言っていますが、「保守」は切り札となる便利な記号なのです。大切なのは、わが国の未来を変えたいというひたむきな情熱です。観念ではなく、行為です。本書は一人の非政治的人間の私心なき訴状にほかなりません。
本書の具体的な成立次第は、第一部・と・の■一において詳(つまび)らかにしてあるので、ここでは控えます。
第二部は、独立した別個のエッセー群です。そのなかの・は、ある雑誌に連載途中だった「現代世界史放談」です。本当はこれで一冊作りたかったのですが、そうなると出版が大分先になるので、ここに収録しました。・の一の題「広角レンズを通せば歴史は万華鏡」は、私の今の心からの実感で、これにより今後また歴史に関する新しい活動ができるのではと自分に期待している切り口の一つです。
ノンフィクション作家の加藤康男氏に緊急対談をお願いしました。本書のきっかけとなった「産経新聞」コラム【正論】「思考停止の『改憲姿勢』を危ぶむ」を書く上で、氏が影の協力者として貢献してくださったからです。詳しい事情や老齢になって目ざましい活動を始められた氏のお仕事などについては、・の冒頭部分をご覧ください。
本書は徳間書店学芸編集部で私の担当である橋上祐一氏の慫慂により、思い立ち、私自身も一冊の組み立てに参加し、成立しました。本はまたたく間にできあがりました。心からありがとう、と申しあげたい。
二〇一七年八月十五日
西尾幹二
若い人への言葉
DHCテレビで、堤堯さんの司会で行われていた「やらまいか」という座談討論番組が本年3月末に終了した。最終回で各レギュラーに「若い人への言葉」が求められた。私は欠席だったので乞われて言葉のみ送った。司会者が朗読して下さった由である。
若い人に期待するのは日本の歴史を取り戻すことです。今、日本の歴史は正当に語られることがなく、ほとんど消えかかっています。しかしだからといって徒らに日本の良さを主張すればよいということではありません。日本を外から眺めることがまず大事です。若いうちに外国で暮して下さい。進んで留学して下さい。
外から日本を眺めると、他の外国でどこでも普通にやっていることが日本にだけない、というようなことが数多くあることにきっと気がつくでしょう。だから、そこだけ外国に学び、真似すればそれでよい、ということではありません。むしろ逆です。外国からは学ぶことのできないもの、どうしても真似することができないものが確実に存在します。それは何か、日本の歴史の中にさぐり、発見し、そこを基盤にもう一度日本を外から見直して下さい。そうすれば日本の欠陥も、長所や特徴もより明確に分るようになるでしょう。
外からと内からのこうした往復運動を繰り返して下さい。貴方はきっと歴史を知ることが自分を知ることと同じだということに気がつくようになるでしょう。
石原萠記さんへの感謝
石原萠記さんが亡くなった。5月20日に東海大学校友会館でお別れの会が開かれた。その際「皆さまからいただいた思い出の一言」と題した200人余の文章を蒐めた小冊子が配られた。私もその中に参加していた一人だった。私の「思い出の一言」は次の文章である。
29才のときに書いた「私の『戦後』観」が自由新人賞に選ばれたとき私は翌年夏にドイツに留学することが決まっていた。選者は竹山道雄、福田恆存、林健太郎、平林たい子、関嘉彦、武藤光朗の諸先生であったが、石原萠記編集長も正式に選者の一人だった。
私はドイツから編集長の指示にしたがい3本のドイツ観察記を送った。右翼政党NPDの初登場をめぐる喜劇的スケッチもその中にある。(単行本未収録、全集で拾い上げた。)
私は自分の留学を文明論的考察の対象にしようと意気込んでいた。思えば幼い気負いである。鴎外や荷風のヨーロッパ体験がたえず念頭にあった。まだそういう自尊のポーズが失われないですむような時代だった。帰国したらすぐに連載を始めたい。それを可能にしてくれたのは『自由』であり、わけても石原編集長だった。
こうして出来上がったのが『ヨーロッパ像の転換』である。石原氏は帰国した私にやさしかった。1960年代は周知の通り左翼全盛の時代だった。しかし今と違って、左翼にも相手の存在を尊重する言葉への信頼がまだあった。石原氏はその嵐の中をもまれて戦った戦士だった。
60年代は『世界』と『自由』が知的言論界を二分した。その安定した対決のバランスを壊したのは70年安保であり、三島事件だった。にわかに言葉より行動が求められる気流の変化が生じ、それはいたずらにささくれ立ち、次に無気力、無関心、無感動のムードに取って替わるようになっていった。
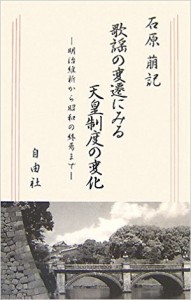
もうひとつのポピュリズム
大学教養部時代の友人のY君(西洋史学科へ進んでテレビ会社に勤務した旧友)から6月9日に学士会夕食会の講演会でEUに関する講演を聞いたといい、そのときのペーパーと講師の論文を送ってきた。講師は北大の遠藤乾さんという国際政治学者で、最近中公新書で『欧州複合危機』という本を出しているらしい。私はその本を読んでいないが、Y君には次のような感想を送った。一枚の葉書の表裏にびっしり書くとこれくらいは入るのである。
拝復 欧州新観察のペーパー及論考一篇ありがとうございます。フランスの選挙結果は、私には遠藤氏と違って、健全のしるしではなく、フランスのドイツへの屈服、ドイツと中国(暗黒大陸)との野心に満ちた握手、反米反日の強化、等々でフランスには幸運をもたらさないように思えてなりません。
フランスは衰弱が加速している国です。それなのに自由、平等、博愛のフランス革命の理念に夢を追いつづける以外に「ナショナルアイデンティ」を見ることのできない今のフランス国民は、ルペン支持派とは別の、もう一つのポピュリズムに陥っているのではないでしょうか。マクロンもまたポピュリズムの産物だと私は言いたいのですが、いかがでしょうか。
フランスは三つに分裂している国です。(A)ドイツに支配されてもいい上流特権階層(B)反独・国境死守のルペン派(C)共産党系労働者階層の三つで、この三分裂は欧州各国共通です。一番現実的なのは(B)で、(A)(C)はフランス革命前からずっとつづく流れです。
(A)が勝ったので、イスラム系移民が増大し、フランス経済は悪化し、マクロンは早晩窮地に立たされるのではないでしょうか。
以上 勝手ご免
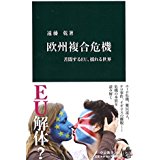
目ざとい「朝日」の反応
私は産經新聞6月1日付(前掲)記事において、次のような文章を最後に加えておいた。勿論これは削除されたが、文章の分量が完全にはみ出ていたので、この件の削除に私は異論はない。たゞそこで示唆していた内容がメディアのその後の小さな動きに関連していたので、再録しておく。
安倍氏は第一次内閣のとき、左翼へ「翼(ウィング)」を広げると称して野党やメディアに阿り、かえってそこを攻撃の対象とされ、他方、味方である核心の保守層からは愛想を尽かされた。今またまったく同じことが始まっている。
読者は次のようなことを思い出して下さるだろうか。第一次安倍内閣のころ安倍氏は、目立たぬ時期にあらかじめ靖国に行っておいて、「靖国に行ったとも行かなかったとも自分は言わない」と煙幕を張り、間もなく村山談話、河野談話を自分は認めると発言し、祖父の戦争犯罪をまで認知してしまった。いったい安倍さんはどうなっちゃったんだろう、と保守の核心層はひどくびっくりもし、がっかりもしたことを皆さまは覚えておられるだろうか。
これが「ブレーン」と称する5-6人の取り巻き言論人のアイデアに基づく戦略的発言であったことは後日だんだん分ってきた。こんな姑息なことはしなければ良いのに、と第一次安倍内閣を歓迎していた私などは落胆したものだった。5-6人の取り巻きの名前なども新聞その他に公表されるようになった。天下周知の事柄になった。
そこで、私の今回の産經発言だが、これにただちに反応したのは朝日新聞(6月4日付二面)で、私からの引用の後に、期せずして次のような内容が記されているの知った。私は新たな発見に目を見張った。
一方、首相を支えてきた保守論壇にとっては、9条2項削除を含む抜本改正が主流で、今回の提案は「禁じ手」(荻生田光一官房副長官)だった。論客の一人、西尾幹二氏は6月1日付の産経新聞で、首相の9条改正案を「何もできない自衛隊を永遠化するという、空恐ろしい断念宣言」「腰の引けた姿勢」と批判した。だが、首相には、戦後70年談話、慰安婦問題での日韓合意に続き、反発は自身が抑えられるという読みがある。事実、首相提案の環境整備ともいうべき動きが進んでいた。
「憲法改正には2年ほどしか時間がない。公明にも配慮することにもなるが、現憲法に欠けた言葉を挿入するだけで、目的をある程度達成することができる」
参院選後の昨年7月末、首相のブレーンと言われ、日本会議の政策委員でもある伊藤哲夫氏が講演で語った言葉が、関連団体のフェイスブックのページに残る。
この時、一緒に講師を務めた西岡力・麗澤大客員教授は翌月、新聞紙上で9条1、2項を残し、3項に自衛隊の存在を書き込む案を例示した。
伊藤氏は9月、自身が代表を務めるシンクタンクの機関紙に「『三分の二』獲得後の改憲戦略」とする論考を発表。「改憲はまず加憲」からと前置きしたうえで、9条に、3項として自衛隊の根拠規定を加える案を提言。「公明党との協議は簡単ではないにしても進みやすくなるであろうし、護憲派から現実派を誘い出すきっかけとなる可能性もある」と説いた。
伊藤氏とかつて全共闘に対抗する学生運動を共にした仲間で、首相側近の衛藤晟一首相補佐官はこのころ、太田氏にささやいた。「9条は(自衛隊の)追加ということでお願いします」
憲法9条1項、2項を残して3項を新設するという5月3日の安倍発言にはまたしても、ブレーンと称する人々の入れ智恵があったのである。安倍さんは自分で考えたのではない。他人にアイデアを与えられている。「今まったく同じことが始まっている」と私が産經論文の結びに書いた一文は証拠をもって裏付けられた形である。
森友学園も加計学園もそれ自体はたいした事件ではないと私は思う。けれども思い出していたゞきたい。第一次安倍内閣でも閣僚の事務所経理問題が次々とあばかれ、さいごに「バンソウ膏大臣」が登場してひんしゅくを買い、幕切れとなったことを覚えておられるだろう。野党とメディアは今度も同じ戦略を用い、前回より大規模に仕掛けている。
同じ罠につづけて二度嵌められるというのは総理ともあろうものが余りに愚かではないだろうか。しかも同じ例のブレーンの戦略に乗せられてのことである。
憲法改正3項新設もこの同じ罠の中にある。
安倍さんは人を見る目がない。近づいてくる人の忠誠心にウラがあることが読めない。「脇が甘い」ことは今度の件で広く知れ渡り、今は黙っている自民党の面々も多分ウンザリしているに相違ない。
保守の核心層もそろそろ愛想をつかし始めているのではないだろうか。櫻井よしこ氏や日本会議は保守の核心層ではない。
北朝鮮の脅威が増す中、9条2項に手をつけない安倍晋三首相の改憲論は矛盾だ

平成29年6月1日 産経新聞 正論欄より
評論家・西尾幹二
北朝鮮情勢は緊迫の度合いを高めている。にらみ合いの歯車が一寸でも狂えば周辺諸国に大惨事を招きかねない。悲劇を避けるには外交的解決しかないと、近頃、米国は次第に消極的になっている。日本の安全保障よりも、自国に届かないミサイルの開発を凍結させれば北と妥協する可能性が、日々濃くなっているといえまいか。
今も昔も日本政府は米国頼み以外の知恵を出したことはない。政府にも分からない問題は考えないことにしてしまうのが、わが国民の常である。が、政府は思考停止でよいのか。軍事的恐怖の実相を明らかにし、万一に備えた有効な具体策や日本独自の政治的対策を示す義務があるのではないか。
≪≪≪防衛を固定化する断念宣言だ≫≫≫
そんな中、声高らかに宣言されたのが安倍晋三首相の憲法9条改正発言である。しかしこれは極東の今の現実からほど遠い不思議な内容なのだ。周知のとおり、憲法第9条1項と2項を維持した上で自衛隊の根拠規定を追加するという案が首相から出された。「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」が2項の内容である。
この2項があるために、自衛隊は手足を縛られ、武器使用もままならず、海外で襲われた日本人が見殺しにされてきたのではないだろうか。2項さえ削除されれば1項はそのままで憲法改正は半ば目的を達成したという人は多く、私もかねてそう言ってきた。
安倍首相は肝心のこの2項に手を触れないという。その上で自衛隊を3項で再定義し、憲法違反の軍隊といわれないようにするという。これは矛盾ではないだろうか。陸海空の「戦力」と「交戦権」も認めずして無力化した自衛隊を再承認するというのだが、こんな3項の承認規定は、自ら動けない日本の防衛の固定化であり、今までと同じ何もできない自衛隊を永遠化するという、空恐ろしい断念宣言である。
首相は何か目に見えないものに怯(おび)え、遠慮し、憲法改正を話題にするたびに繰り返される腰の引けた姿勢が今回も表れたのである。
≪≪≪政治的配慮の度が過ぎないか≫≫≫
「高等教育の無償化」が打ち出されたのも、維新の会への阿(おもね)りであるといわれるとおり、政治的配慮の度が過ぎている。分数ができない大学生がいるといわれる。高等教育の無償化はこの手の大学の経営者を喜ばせるだけである。
教育には「平等」もたしかに大切な理念だが、他方に「競争」の理念が守られていなければバランスがとれない。国際的にみて日本は学問に十分な投資をしていない国だ。とはいえ大学生の一律な授業料免除は憲法に記されるべき目標では決してない。苦しい生活費の中から親が工面して授業料を出してくれる、そういう親の背中を見て子は育つものではないか。何でも「平等」で「自由」であるべきだとする軽薄な政治的風潮からは、真の「高等教育」など育ちようがないのである。
もう一つの改憲項目に「大災害発生時などの緊急時に、国会議員の任期延長や内閣の権限強化を認める」がある。趣旨は大賛成だが、真っ先に自然災害が例に掲げられ、外国による侵略を緊急事態の第一に掲げていない甘さ、腰の引け方が私には気に入らない。
明日にも起こるかもしれないのは国土の一部への侵略である。憲法に記載されるべきはこの事態への「反攻」の用意である。
ちなみにドイツの「非常事態法」は外国からの侵略と自然災害の2つに限って合同委員会を作り、一定期間統率権を付与するということを謳(うた)っている。ヒトラーを生んだ国がいち早く“委任独裁”ともいうべき考え方を決定している。
≪≪≪2項削除こそが真の現実的対応≫≫≫
今の国会の混乱は政府が憲法改正の声を自ら上げながら、急迫する北朝鮮情勢を国民に知らせ、一定の覚悟や具体的用意を説くことさえもしようとしないため、何か後ろめたさがあるとみられて、野党やメディアに襲いかかられているのである。中途半端な姿勢で追従すれば、かえって勢いづくのがリベラル左派の常である。
現実主義を標榜(ひょうぼう)する保守論壇の一人は『週刊新潮』(5月25日号)の連載コラムで「現実」という言葉を何度も用いて、こう述べている。衆参両院で3分の2を形成できなければ、口先でただ立派なことを言っているだけに終わる。最重要事項の2項の削除を封印してでも、世論の反発を回避して幅広く改憲勢力を結集しようとしている首相の判断は「現実的」で、評価されるべきだ-と。
だが果たしてそうだろうか。明日にも「侵攻」の起こりかねない極東情勢こそが「現実」である。声を出して与野党や一部メディアを正し、2項削除を実行することが、安倍政権にとって真の「現実的」対応ではあるまいか。憲法はそもそも現実にあまりにも即していないから改正されるのである。
日本の保守は、これでは自らが国家の切迫した危機を見過ごす「不作為加憲」にはまっているということにならないか。(評論家・西尾幹二 にしおかんじ)
施線部分は、私の書いた原文では、
「櫻井よしこ氏は五月二十五日付『週刊新潮』で、『現実』という言葉を何度も用い、こう述べている」と書かれていました。櫻井氏の名前は出さないで欲しい、という新聞社の要望に従い前記のように改めました。要望は、同じ正論執筆メンバー同志の仲間割れのようなイメージは望ましくないからだ、という理由によるものでした。周知の通り私は批判する相手の名を隠さない方針なので、少し不本意でした。名を伏せるとかえって陰険なイメージをかき立てるのではないかと憂慮するからです。
