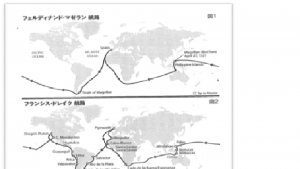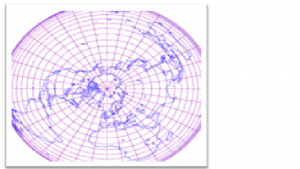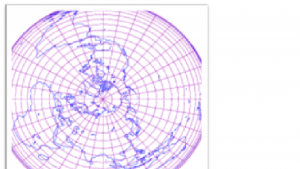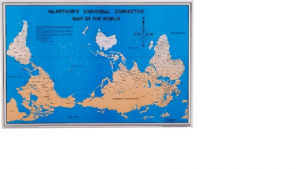(5-1)本を読むことは、何事かを体験するための手段であり、ある意味では最も効率の低い媒体であって、それ以上でも以下でもない筈なのに、どういうわけか端的にわれわれの自己目的とさえなってしまう。それほどにもわれわれを取り巻いている言葉の世界は層が厚く、われわれは現実から無言の裡に距てられているためだともいえよう。
(5-2)教養主義こそが今日の教養の衰弱の原因である。
(5-3)私たち末流の時代の知識人は、ともあれ他人の言葉を手掛かりにしてしか物事を考えることができない(従って物事を書くことも出来ない)ことに慣れ切ってしまっている。私たちは研究とか、学問とか、評論とか称して、何か創造的に物事を考えた積りになっているが、所詮は古書と古書の間隙を逍遥しているだけである。今日に遺されているのは所詮古人の言葉にすぎまい。しかし言葉は何かの脱け殻であって、実体ではないのだ。しかもこの頼りない、表皮でしかない言葉をあれこれ吟味するのは、言葉の分析それ自体が目的ではなく、言葉の届かない、その先にある何かに接近することが本来の目的だということに、いったい今日の学者、批評家、知識人はどれだけ気がついているだろうか。
(5-4)歴史は客観的事実そのものの中にはない。歴史家の選択と判断によって、事実が語られてはじめて、事実は歴史の中に姿を現わす。その限りで、歴史はあくまで言葉の世界である。けれども、歴史家の主観で彩られた世界が直ちに歴史だというのではない。そもそも主観的歴史などは存在しない。歴史家は客観的事実に対してはつねに能う限り謙虚でなくてはならないという制約を背負っている。客観的事実と歴史家本人とはどちらが優位というのでもない。両者の間には不断の対話が必要な所以である。
(5-5)私たちはヨーロッパ近代を自分の前方に見据えながら、同時に自分の背後に克服していかなくてはならないという二重の芸当を演じて来たし、今なお演じつつある。
(5-6)ヨーロッパ的な味附けだけをしただけの日本の古典論とか、自分が近代的教育を受けて来たにも拘わらず、近代ヨーロッパからの「異世界」への問い掛けにあまり敏感でない自閉的な日本文化論などが、いささか無反省に流布しているのが、当代の知性の特徴であるように私には思える。
(5-7)ニーチェの本は何処から読み始めてもよいし、何処で読み終わってもよいのではないか。丁度音楽は何処から聴き出してもわれわれを引き摺り込んでしまうように、ニーチェの著作はあらゆる処に入口があり、出口があるのだ。論述的な著作の場合でも、文の構造が基本においてアフォリズムだということを物語っていよう。
(5-8)現在を否定し、批判する行為が、とりもなおさずそのまま理想への道だということが凡庸の徒にはどうしても分からない。代案は何か。具体的な方策を示せ。万人が歩める道を教えよ。彼らは必ず目的でなく手段を聞きたがる。(中略)自分で道を試すのではなく、人に道を教えてもらわなくては安心しない。
(5-9)現代はいわば価値の定点がどこにもない。すべての要素が同時に存在し多様化し、開放され、前進型のあらゆる試みがたちどころに古くなるような時代です。なにかの観念や、特定の視点というものは大抵相対化して、普遍的なものとしては成り立ちにくい。が、その反対に、いかなる視点も不可能になったという、いわば近代史を通じてくりかえされてきた自己解体の主題でさえが、ルーチンとなり、妙に安定した意匠となって、再検討を要求されている時代だともいえます。あらゆる問が並立しているのが、まさしくこの現代の姿なのです。
(5-10)虚偽なしで人は生きられない。その限りで虚偽は真理である。しかし真理はまた束の間に過ぎ去り、次の瞬間には虚偽に転ずる。
(5-11)真理は体系化できない。真理は容易に伝達し得ないし、認識し得ないなにかである。真理は認識するものではなく、わずかに接触することが出来るにすぎない。真理はときに言葉になり得ないものから、沈黙から、瞬間的に発現する。平生人は真理にあらざるもので表象し、行動する。真理とは生きるために人が時に応じて必要とするイルージョンである。
(5-12)歴史的教養で頭を一杯にして、自分が何をしたいのか、そして何を言いたいのかさえ分らなくなっている現代知識人の懐疑趣味、もしくは自己韜晦癖
(5-13)近世に確立した人間の主体的自我は、やがては自然を、世界を自己の外に客体化し、ねじふせ、加工し、利用する近代科学の自己絶対化をもたらすに及んだ。十九世紀は無反省なまでにその危険が増大した時代である。世界に存在するいっさいのものが主体的学問の対象となり、対象化できない心の暗部や信仰や芸術までをも解剖し、分析した。
(5-14)ギリシア人はつねに超時間的なもの、永遠なもののみを考えた。現在の瞬間に生きることが、同時に永遠につながる。自然は同一のものの周期する世界であり、悠久無辺である。時間には発端もなければ、終末もない。キリスト教世界のように、終末の目的が歴史に意味を与えるのではない。ギリシアにも歴史家はいたが、有限な時間が一つの目的へと向かう多くの人間的出来事の連続として、歴史が意識されたことはなかった。
(5-15)思想は今や趣味の問題でしかなく、人間は生きるために生きる以外にどんな生の課題ももち得ず、またもち得ないことに疑問すら抱かなくなっている。それでいて世間は少量の毒ある刺激をたえず求めるが、しかし本気で毒を身に浴びる者はどこにもなく、なにごとにつけほどほどで、人々は怜悧(れいり)になり、あるいは歴史書に慰めを求め、あるいは永生きするための健康書にうつつを抜かす。
こうした状況を「成熟」とか称して現状肯定する思想家がもてはやされ、その分だけ時代の文化は老衰し、活力を失っていく。だが、にぎやかな鳴り物入りの漫画のような思想は、時代の無目標をごまかすために、人々に一時の快い夢をみさせてくれる。
(5-16)なにもかもが煩わしいからわれわれは差別を恐れ、福祉を唱え、健康を重んじているのであろう。
(5-17)日本にはキリスト教がないからニーチェの言う「神の死」はわれわれの問題ではないという日本人がよくいる。しかし明治以来、近代化の洗礼を受けて、日本人をつつんでいた江戸文化の有機的統一体が失われ、今や国家にも個人にも目的がなく、「彼岸の世界」への信仰ももち得なくなっているのは、まさに現下のわれわれの問題ではないだろうか。「神の死」とはなにも西洋だけの問題ではない。われわれ近代文化全体をつつみこんでいる宿命である。
(5-18)いっさいの現象の仮面を剝いで、裏側の真実を見ようとすること自体が、ひとつの嘘になり、自己欺瞞を招きやすい。
(5-19)本当の不安のうちに生きるとは、ときに仮面を剝いでその裏を覗き見、ときに仮面をそのまま素朴に愛するということを交互にくりかえす以外にはない。いいかえれば、ときにあらゆる真理を疑い、いかなる信念をも使い捨てて、懐疑の唯中に立つかと思えば、ときに嘘と承知でなにかを信じ、いわば手段としての信念を気儘に用いる立場へと転ずる。立場は次から次へと瞬時に変わっていく。どこにも定点はないのかもしれない。
(5-20)一切の価値意識を排除して、純粋に科学的な、厳密に客観的な認識は不可能であるばかりでなく、真の学問にとって有害でさえある。認識には価値観が必要である。と同時に、行動を伴わない単なる認識はけっしてなにかを認識したことにはならない。行動や価値は過去の研究を通じてもなお現在に作用していなければならない。
(5-21)そんなことを言っても、もとより音楽の理解にはなんの助けにもならないが、音楽が一種の文学性(あるいは近代的な感傷性)をもつことによって、かえって音楽自身のために演奏されるようになり、他の従属物でなくなっていったということは、まことに不思議な逆説といえるかもしれない。
(5-22)実人生に敗れた弱い人間、社会の落伍者、失敗者に限って、自分の敗北にも意味があることを別の論理で拡大解釈しようとして、救済を自分以外の世界に求め、自分の弱さから目をそらし、弱点の正当化を試みようとしたがる。これは生命力の衰退のしるしであるが、しかしまた、この自己欺瞞は群をなして、集団力に危険な力として伝播して行く傾向がある。いわば「伝染的な作用をする」のである。
(5-23)デカダンスとは自分で自分を瞞して、眠らせる、麻薬のような世界である。当然、大変に心地良い世界だと言える。そして近代人ほど、幸福の原理でなく快適の原理を求めて倦み疲れている存在もないと言ってよいだろう。
(5-24)真理と名のつくものはことごとくフィクションではないだろうか?物という「概念」が発生したのは、到達できるたしかな「物」が存在しているからではなく、むしろ「物」が存在していないからではないだろうか?同じように、真理という「言葉」が発生したのは、「真理」が認識可能であるためではなく、むしろ逆に、「一つの」真理が必要から捏造(ねつぞう)されたせいではないだろうか?
(5-25)言葉の及ばぬ部分に、言葉を用いることで、なにかの真理が得られたためしはなく、多くの場合には、むしろ逆に、真理(16頁上段から下段「光と断崖」)
にあらざるものに真理という「言葉」を与えただけに終わってしまう(中略)それくらいならむしろ、嘘を嘘としてはっきり自覚した方がよい。言葉の及ぶ部分がどこまでであるかをよくわきまえていることが必要であろう。
(5-26)理解とは理解し得ない自分にまず直面することから始まる、という問い
(5-27)狂気の淵のそば近くまで歩み寄ることによって、正気はかえって明晰になり、洞察の目はますます深く、ますます鋭く物事の核心を捉える
出典 全集第五巻
光と断崖― 最晩年のニーチェ より
「Ⅰ 最晩年のニーチェ」より
(5-1)(9頁下段から10頁上段「光と断崖」)
(5-2)(11頁上段「光と断崖」)
(5-3) (16頁上段から下段「光と断崖」)
(5-4) (24頁下段から25頁上段「光と断崖」)
(5-5) (60頁下段「光と断崖」)
(5-6) (62頁上段「光と断崖」)
(5-7) (97頁上段から下段「幻としての『権力への遺志』」)
「Ⅱ ドイツにおける同時代人のニーチェ像」より
(5-8) (319頁上段)
「Ⅳ 掌篇」より
(5-9) (396頁下段「人間ニーチェをつかまえる」)
(5-10)(429頁上段「私にとって一冊の本」)
(5-11)(429頁上段「私にとって一冊の本」)
(5-12)(453頁下段「「教養」批判の背景」)
(5-13)(472頁上段「「教養」批判の背景」)
(5-14)(474頁下段「「教養」批判の背景」)
(5-15)(478頁下段「ニーチェと現代」)
(5-16)(479頁下段「ニーチェと現代」)
(5-17)(481頁下段「ニーチェと現代」)
(5-18)(486頁上段「実験と仮面」)
(5-19)(487頁上段「実験と仮面」)
(5-20)(493頁上段「批評の悲劇」)
(5-21)(496頁下段「ニーチェのベートーヴェン像」)
(5-22)(501頁下段から502頁上段「自己欺瞞としてのデカダンス」)
(5-23)(504頁上段「自己欺瞞としてのデカダンス」)
(5-24)(516頁下段「言葉と存在との出会い」)
(5-25)(522頁下段「言葉と存在との出会い」)
(5-26)(532頁上段「和辻哲郎とニーチェ」)
「後記」より
(5-27)(559頁)