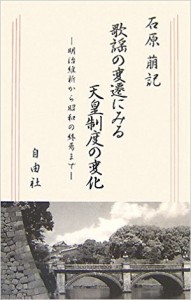もう一つ大事なことは介護や家事労働のような特別の訓練を必要としない外国人は現地に於ける食い詰め者なのです。つまり、各国が棄民したいような人達、外に出して捨ててしまいたいような労働力であり、これらの人達は例外なく日本に来た後に不法滞在者になり、更に生活保護受給者になります。そこまで考えているのでしょうか。
私は最近知ってびっくりしたのですが、介護のために政府は補助金を2兆年介護の事業主に支払っているそうです。介護に携わる介護士の賃金をあげるためなら良いのですが事業主に支払っているのです。プールされたこのお金はどこに消えているのでしょうか。
介護士になりたがらないのは労働がきついわりに賃金が低いからで、報酬が良ければやりたい人はいくらもいるのです。看護師も同様です。現在でも平均賃金は上昇していません。外国人を入れることはデフレ脱却に逆行しています。ユニクロや外食のワタミが人手不足で困って、正規労働者をふやし、賃金を上げましたが、これがいい証拠です。外国人を入れなければ、全国全産業で賃金が上がり、消費が増え、若者は結婚する気になります。
安倍さんはこの原則が分かっているのでしょうか。農業問題でも非常に疑問に思うのは、リンゴとかおいしいお米を中国に売るとか言っておりますが、それは悪いことではないかもしれません。ただ、本来日本の農業問題はそんなことでしょうか。日本の農地はあり余っています。これを株式会社にするということに対して農業団体が反対しており、動かない訳ですが、怖いのはそこに外資が入ってくることであり、それだけ厳格にチェックすれば農業の大型化は必要なことではないでしょうか。おいしいコメやリンゴを作って外国に売るなんてことは総理大臣が考えるようなことではありません。目の色を変えてでも次の世代の我が国民の主要食糧は確保出来るのかということが最大の課題です。これから地球全体の人口は20億人増えるといわれております。20億人増える人口に対してもう食糧の生産は限界にきております。
中国政府は食料やエネルギーの確保に目の色をかえています。ですからベトナムを襲撃して石油を掘ろうとしているのです。フロンティアの拡大が無くなっているのですから、自分の国が必要な食糧やエネルギー獲得のためには戦争も辞さないといっているのです。
ベトナム沖や尖閣で起こっていることはそのことなのです。13億の民にはまだ激しい「需要」があります。「フロンティア」があります。だから世界の眼はいぜんとして中国に注がれ、アジアがたとえ戦争になってもそこでまだ儲けようと、例えばヨーロッパ人は今現に考えているでしょう。
ポルトガルの海の帝国がイギリスの海賊(パイレーツ)に引き継がれた「フロンティア」探しは、南北アメリカという新大陸への幻想によって推進され、四百年が経過しました。そしてすべての空間は究め尽くされ、金融や情報による地球支配も終わりに近づいています。中国が終われば日本は助かりますが、しかしもう新しいことは何も起こりそうもありません。「フロンティア」の消えた世界はパイの奪い合いは陰惨になり、静かに資本主義が死を迎えることになります。
了